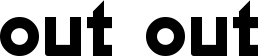作曲家・即興演奏家のRobert Stillmanは、Apple創業者スティーブ・ジョブズの伝記からインスピレーションを受け、新作アルバム『10,000 Rivers』をOrindal/Kit Recordsからリリースします。このアルバムは、ジョブズの人生の瞬間やパラダイムに直接応答する、文化的批評と音響的伝記を兼ねた作品です。Stillmanは、ジョブズのテクノロジーデザインを「乱雑な現実を、合理化され、死のない、かろうじて物理的なものに置き換えようとする意志の表現」として捉え、そのオルタナティブな物語を提示します。アルバムからの最初のシングルは2026年1月9日にリリース予定で、ビデオはJames Bridleが監督しています。
アルバムの音楽性は、80年代から90年代初頭のBilly Ocean、Gloria Estefan、10ccといったスムース・ミュージックに影響を受けています。Stillmanは、この時代を「人間とデジタルの間のナイフの刃」と呼び、ジョブズの全盛期と同時期に主流となったこの音楽の野心的で単調な特質を遊び心をもって解体します。サウンドは、合成アルペジオとアコースティックな即興が並び立ち、不快なオートチューンの子守唄や、Brian Wilson的なカリフォルニア・ドリーミングを解体した不気味なフリージャズの狂騒へと展開します。
『10,000 Rivers』は、ライブ感とパフォーマンス性を追求するため、1/2インチの8トラック・テープに録音され、リアルタイムでミックスダウンされました。この結果、一人の男の生涯と、それが定義するに至ったより広範な社会的価値観への思索的で、ジャンルレスなサウンドトラックとなっています。Thom YorkeやJonny Greenwood(The Smile)との最近のコラボレーションでも知られるStillmanにとって、本作は「ほころびながらも不死を設計しようとする人類の傲慢さへの悲歌」であり、彼の最も野心的で特異なプロジェクトの一つです。