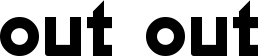締め切りという「重圧」が導き出した、3日間の純粋な即興記録。Index For Working Musik が放つ、本編を凌駕する熱量を孕んだ「アンチ・フォーマリズム(反形式主義)」のドキュメント
ロンドンを拠点に活動するアンチ・フォーマリスト(反形式主義)集団、Index For Working Musikが、4月3日にTough Loveからリリースされるアルバム『Bunker Intimations II』より、最新シングル「Geordie Vision」を発表しました。本作はセカンドアルバム『Which Direction Goes The Beam』の姉妹盤であり、元々は同作の初回限定アナログ盤にのみ付属していた貴重なカセット音源が、待望の単独リリースとなります。
収録された50分に及ぶ録音は、2025年3月のわずか3日間という、極めて厳しい締め切りの重圧下で制作されました。すべての楽曲はその場で即興演奏され、即座にミックスダウンされており、作為的な加工を排した「その瞬間」の記録となっています。この切迫した状況下で生まれた生々しいエネルギーは、制作陣の一部から「本編のアルバムを凌駕している」と評されるほどの完成度を誇ります。
先行シングル「Geordie Vision」は、彼らの実験的で妥協のない姿勢を象徴する一曲です。計算された形式主義に抗い、即興が生み出す予測不能な展開と剥き出しのグルーヴが、リスナーをロンドンの地下シーンの深淵へと引き込みます。単なるおまけの音源集という枠を超え、アーティストの純粋な創造性が爆発した瞬間のドキュメントとして、今改めて世に問われる重要な作品です。
アイルランドの静寂から、轟音と叙情が交錯する新境地へ。ポストロックの残響にシューゲイザーの色彩を重ね、newhvn が描き出す広大なインディー・ロックの地平
アイルランドの辺境から登場したnewhvnが、デビューアルバム『Spring Time Blues』からの第1弾シングル「Skin Off the Bone」をリリースしました。ポストロック・バンドの残響から結成された彼らは、その大気的なルーツにシューゲイザーやポストハードコアの要素を融合。これまでにヨーロッパ、イギリス、アジアを巡る広範なツアーを行い、Touché AmoréやTrauma Rayといった実力派バンドとステージを共にする中で、着実にその実力を磨き上げてきました。
今作『Spring Time Blues』は、PinegroveやThe War on Drugsといったアーティストからの影響を独自の広大なサウンドへと昇華させた作品です。スコットランドのルイス島にあるBlack Bay Studiosにて、プロデューサーのTom Peters(Alpha Male Tea Party)と共にレコーディングを実施。全10曲にわたる収録楽曲は、ワイドスクリーンなインディー・ロックの開放感と、彼らの出発点であるポストロック特有の感情的な激しさを絶妙なバランスで共存させています。
アイルランドのアンダーグラウンド・シーンと長年の国際的なツアー経験によって形作られた彼らのサウンドは、カラーヴァイナルとしてもリリースされるこのデビュー作で見事な結実を見せています。静寂と轟音を使い分けるダイナミズムを保ちつつ、よりパーソナルでエモーショナルな物語を紡ぎ出す本作は、ポストロックの枠を超えて新たな地平を切り拓く、newhvnにとって極めて重要なステートメントとなっています。
理性と狂気の境界に浮かび上がる、退廃的でセクシーな白昼夢。Douglas Diamond が放つ、セックスと陰謀がインフラとして機能する架空の楽園「Diamondland」への招待状
Douglas Diamondが、ニューEP『Welcome to Diamondland』からの最新シングル「All Night」をリリースしました。Diamondland(ダイヤモンドランド)は、理性的な判断の境界線上に存在する、セクシーで予測不能なアートが許されたファンタジーの世界です。カウボーイハットを被った過去不明のバーテンダーや、誰にも聴かれないヒット曲を歌うクルーナー、そして空に不吉な線を描くケムトレイルなど、倒錯した日常と陰謀が入り混じる奇妙な情景が描き出されています。
本作は、セックスやパラノイア(被害妄想)が社会のインフラとして機能しているような、極めて映画的な世界観を持っています。それはまるで、低予算で制作された『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』や、最初の一音が鳴る前から不穏な空気が漂う深夜のロードハウスでのライブのようです。不完全さや危うさをあえて内包することで、聴き手を現実離れした倒錯的な夢幻の世界へと誘う、強烈なステートメントとなっています。
Aftertaste – “Augusta”
フランスとイギリスにルーツを持つフォーク・アーティストAugustaが、5月8日リリースの新作EP『Make a River of My Spine』から、最終先行シングルとなる「Aftertaste」を発表しました。本作は、深い悲しみを経た後にふと感じる「幸福への静かな罪悪感」をテーマにしています。愛の記憶が残り香(アフターテイスト)のように漂う中で、少しずつ喜びを受け入れていく心の機微を、彼女の特徴である繊細なギターワークと思慮深いメロディで描き出しています。
サウンド面では、抑制されたフォークのテクスチャーが穏やかに流れ、感情が自然に湧き上がるのを待つような、ゆったりとした空間が保たれています。歌詞の中では、愛する人の笑い声に自分を重ね合わせる親密な瞬間や、かつての痛みに縛られながらも新しい幸せに戸惑う姿が綴られています。解決を急がず、聴き手が自らの感情を辿るのを許容するような、優しさと強さが同居した Augusta らしい一曲です。
To Athena – “Collide”
スイスを拠点とするアーティストTo Athenaが、5月22日にリリース予定のニューアルバム『Have I Lost My Magic』から、第3弾シングル「Collide」を3月13日に発表しました。本作は、彼女が自身の「バーンアウト(燃え尽き症候群)」について初めて公に語った重要な楽曲です。限界を超えて上へ、より高くへと突き進もうとする衝動が、ついに「空と衝突(Collide)」してしまう瞬間を描いており、疲弊した感覚を壊れやすくも力強い音楽的エネルギーへと昇華させています。
サウンド面では、スローモーションの嵐のようなダイナミズムを湛えたワルツが展開されます。幾重にも重ねられたストリングスが重厚な層を成す一方で、彼女の代名詞であるクリアで情感豊かな歌声が混沌を貫き、優雅な憂いを感じさせます。初期に注目を集めた『Aquatic Ballet』の深い情緒へと回帰しつつ、脆さと強さの両面を力強く提示した本作は、嵐のような日々を生き抜いた後に残る「内なる光」の在り方を問いかける、アルバムの核をなすステートメントとなっています。
Charm – “Speechless (Tongue Tied)”
ノースカロライナ州グリーンズボロを拠点とするCaleb Buehnerのソロプロジェクト、Charmの新曲「Speechless (Tongue Tied)」は、作詞・作曲からミックス、マスタリングまでを彼自身が手掛けた、DIY精神あふれる一曲です。サウンド面ではシューゲイザーやベッドルーム・ロック、さらにはディスコ・ロックの要素を融合させ、ドリーミーでありながらもリズミカルな高揚感を演出。9時から5時まで蛍光灯の下で働き、時間が溶けていくような日常から、太陽の光の下へと逃避したいという切実な願いを、爽快なインディー・ロックの質感で描き出しています。
歌詞の中では、窮屈な仕事やルーティンから解放され、新鮮な空気を吸うことで頭の中のノイズを消し去る瞬間が描かれていますが、その一方で、あまりの眩しさや感情の昂ぶりに「言葉を失う(Speechless)」というパラドックスが表現されています。何かに模倣するのではなく、一歩踏み出して自分自身の人生を掴み取ろうとする前向きなメッセージが込められており、充電切れ寸前の心に「太陽の光」という処方箋を与えるような、内省的かつエネルギッシュなトラックに仕上がっています。
Machine Girl – “Come On Baby, Scrape My Data” (Dj Smokey Remix)
Machine GirlとDj Smokeyという、インターネット・アンダーグラウンドの異才二人がタッグを組んだ本リミックスは、原曲のカオティックなデジタル・ハードコアに、Dj Smokey特有のトリッピーなトラップ・グルーヴを注入した衝撃作です。「Come On Baby, Scrape My Data」という挑発的なタイトルが示す通り、デジタル監視やデータ抽出が蔓延する現代社会への皮肉を、歪んだ電子音と中毒性の高いミーム的サンプリングで描き出しています。
サウンド面では、Machine Girlの暴力的なBPMとDj Smokeyの不気味なシグネチャーサウンドが衝突し、まるで壊れたサーバーの中でダンスを踊っているような、焦燥感と高揚感が同居する音像を生み出しています。単なるダンスミュージックの枠を超え、加速主義的なインターネット・カルチャーの最前線を体現しており、デジタル世界の深淵を覗き込むような破壊的かつ没入感のあるリスニング体験を提供しています。
Tiga – “FRICTION”
カナダ・モントリオールの重鎮Tigaが、10年ぶりとなる待望のニューアルバム『HOTLIFE』から、最終先行シングル「FRICTION」を本日リリースしました。Jesper DahlbäckやPrioriと共作し、Patrick Hollandが追加制作に参加した本作は、これまでの矢継ぎ早なフックとは一線を画すリラックスしたアプローチが特徴です。「生きるだけで多大なコストがかかる」という現代社会の困難な状況を、彼らしい軽快さと深い感情が同居する絶妙なバランスで表現しています。
この楽曲は、ダンスミュージックが日常の重荷を軽減し、現実逃避の場として機能し続けていることへの賛歌でもあります。4月17日にTurbo RecordingsとSecret City Recordsから共同リリースされるアルバム『HOTLIFE』には、Boys Noize、Fcukers、Maara、MRDといった豪華ゲストも参加予定。先行曲「ECSTACY SURROUNDS ME」や「HOT WIFE」に続く本作は、現代の「摩擦(フリクション)」と「緊張」の中で、私たちが求めるべき癒やしと連帯をクールなヴァイヴで提示しています。
Linda Wolf – “Lonely”
Linda Wolfの新曲「Lonely」は、最も残酷な孤独の形の一つである「二人でいる時に感じる孤独」をテーマにした、繊細かつ強烈なインディー・ポップ・トラックです。自分の真実を語っても受け入れられず、逆に突き放されてしまう瞬間に生まれる空虚さを描いています。痛みに真正面から向き合いながらも、決して崩れ去ることのない、静かな決意と「明晰さ」がこの曲の核となっています。
サウンド面では、まるで静かな部屋の中にいるような親密な空間が演出されています。心の亀裂を浮き彫りにするような温かくも鋭いアコースティック・ギターを中心に、ドラム、ベース、シンプルなピアノ、そして微かなシンセがメロディを優しく包み込む層を成しています。Linda Wolfのクリスタルのように澄んだ歌声が、削ぎ落とされたミニマルな構成の中で際立ち、剥き出しの感情と力強い意志を聴き手に届けています。
beabadoobee – All I Did Was Dream Of You (feat. The Marías)
Beabadoobeeが、The Maríasとタッグを組んだ新曲「All I Did Was Dream of You」をリリースしました。2024年のアルバム『This Is How Tomorrow Moves』以来となる本作は、トリップ・ホップとオルタナティブ・ロックの要素を融合させた、極めて雰囲気豊かなサウンドが特徴です。ギター、ドラム、シンセが織りなすレイヤーの上を、彼女の魅惑的なボーカルが漂い、「あなたとならすべてが簡単」と親密な関係性を歌い上げています。
このプロジェクトは、ボーカルのMaría Zardoyaがソロプロジェクト「Not for Radio」を始動させて以来、沈黙を守っていたThe Maríasにとっても久々の新展開となります。楽曲と共に公開されたミュージックビデオは、リトアニアのヴィリニュスで撮影。彼女の長年のコラボレーターであるJake Erlandと、現地のディレクターAboveGroundが共同監督を務め、楽曲の持つドリーミーで質感のある世界観を視覚的に表現しています。