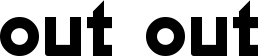Paula Kelleyは、1992年のシューゲイズの傑作『Delaware』でヴォーカルとギターを担当したDrop Nineteensのオリジナル・コアメンバーとして最もよく知られています。このアルバムリリース直後にバンドを脱退し、ソロ活動に専念。2001年の『Nothing/Everything』、2003年の『The Trouble With Success Or How You Fit Into The World』といったソロアルバムを発表しました。そして、20年後にDrop Nineteensの復活アルバム『Hard Light』に参加した後、この度、20年以上ぶりとなる自身のソロアルバム『Blinking As The Starlight Burns Out』を3月にリリースします。
先行シングルとして公開された「Party Line」は、ドリーミーなサウンドが特徴です。Kelleyは現在12年間断酒していますが、新作『Blinking As The Starlight Burns Out』の多くの楽曲は、彼女の薬物使用の歴史にインスパイアされています。「Party Line」の歌詞には、「生きたいけれど安定が欲しい/リスクも欲しいけれど平穏も欲しい、敵意は要らない」という、安定と刺激の間で揺れる葛藤が歌われています。
Kelleyは「Party Line」について、ベースライン、4声のヴォーカル・ハーモニー、広大なサウンドスケープが、ほとんど完成した形で頭に浮かんだと語っています。彼女は、パートごとに録音を進める中で「まるで曲が自らを書いているよう」に感じたほど、制作が順調に進んだ幸運に恵まれたと述べています。この「夢のような歌」は、睡眠中に見る夢ではなく、願い、不安、投影といった願望を通じて、不幸な過去と向き合い、和解するための手段として機能しています。