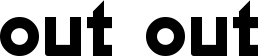a.gris – “bar”
a.grisの新曲「bar」は、3月27日にレーベルGéographieからリリースされるEP『Gris’』からの先行シングルです。a.gris自身が作詞・作曲・プロデュースを手がけ、Tessa Gustinによる追加ボーカルが楽曲に奥行きを与えています。「トラウマのない人生に関わって以来、私は一晩中起きている自分の痛みに花を贈る」といった内省的な歌詞は、Stainless(汚れなき状態)でありながらも、どこか諦念や痛みを抱え、静かに爆発(implode)の瞬間を待つような危うい均衡を表現しています。
サウンド面では、Studio NoirのFlorentin Convertによる録音とMaxime Maurelのミックス&マスタリングにより、研ぎ澄まされた質感が際立っています。「カメラなしで撮影できる守護者」や「見知らぬ人の耳に叫ばれた秘密」といった抽象的で毒のあるフレーズが、洗練されたエレクトロニックなトラックの上で、まるで映画の断片のように響きます。アートワークも自ら手がけるa.grisのトータルな美学が反映されており、都会的な孤独の中に潜む皮肉とドラマを、独自の「ハイパー・コンプロマイズド(過度に妥協した)」なレシピで描き出した一曲です。
don’t get lemon – “Matrimony”
テキサスの3人組による新曲「Matrimony」は、New Orderの脈打つようなビートとPet Shop Boysのロマンティックな距離感を引き継ぎつつ、80年代シンセ・ポップのレンズを通して「絆を維持することの真の代償」を描き出しています。この楽曲が映し出すのは、美しく磨き上げられた理想の愛ではなく、献身が単なる概念から、日々のささやかな決断の積み重ねへと変わる現実的な場所です。愛が壊れやすく、同時に永続的であると感じられる、その複雑な感情の揺らぎがサウンドの核となっています。
歌詞に登場する「水面に浮かぶ花」や「ダクトテープと針金」といった対照的なフレーズは、献身というものが華やかな宣言ではなく、努力や妥協、そして意図によって繋ぎ止められている静かな営みであることを象徴しています。表面上は美しく見えても、その裏側では絶え間ないメンテナンスが必要とされるという「選ぶことの魔法」と「脆さ」の共存。本作は、映画のような完璧な結末ではなく、不器用ながらも即興で形作られていく真実の愛に向けられた、思慮深くも切実なリアクションと言えるでしょう。
Oscar Farrell – “Dream Therapy” (feat. Sampha) (Geogre FitzGerald remix)
George FitzGeraldがリミックスを手がけたOscar Farrellのシングル「Dream Therapy (ft. Sampha)」は、エレクトロニック・ミュージック界の至宝たちが交錯する、幻想的でディープな一曲です。Sampha特有の、魂を揺さぶるようなエモーショナルでハスキーなボーカルを、FitzGeraldが持ち前の洗練されたプロダクションで再構築。オリジナルの持つ内省的なムードを活かしつつ、繊細なビートと幾層にも重なるシンセ・テクスチャによって、夢と現実の境界を彷徨うようなダンスフロア・アンセムへと昇華させています。
本作は、単なるリミックスの枠を超え、聴き手を深い瞑想状態へと誘う「音のセラピー」としての側面を持っています。FitzGeraldらしいメランコリックでありながらも推進力のあるグルーヴは、Samphaの歌声が持つ「祈り」のような響きをより鮮明に際立たせ、都会の夜の孤独や静かな高揚感に完璧にマッチします。二人の類まれなる才能が融合したこのトラックは、深夜のリスニングからフロアのピークタイムまで、幅広いシーンで聴く者の心に深い余韻を残すことでしょう。
Rum Jungle – “Coal Dust”
オーストラリア・ニューカッスル出身のインディー・ロック/オルタナ・バンドRum Jungleが、新曲「Coal Dust」をDowntown Musicよりリリースしました。全英チャートを賑わせ、多くの年間ベストアルバムにも選出された2025年のデビュー作『Recency Bias』に続く本作は、これまでの彼らよりもさらに忍耐強く、空間的で、感情に真っ直ぐな進化を遂げた一曲。自分を形成した場所への、逃げ出したいほどの衝動と抗えない郷愁の狭間で揺れる、ほろ苦い感情が描かれています。
フロントマンのBennyは本作について、若さゆえに故郷を制約と感じて飛び出そうとするものの、大人になるにつれてその場所が自分を支える「拠り所」であったと気づく、成長に伴う視点の変化を表現したと語っています。また、カップリングのB面曲「Dumb Waste Of Nothing」は、彼らのルーツであるサイケ/スラッカー・ロックの要素を色濃く反映。進歩と自己省察をテーマにしたこの曲は、深夜のセッションから生まれたリラックスした空気感を纏っており、メイン曲の「記憶と場所」というテーマに対し、「内省と前進」という対照的な側面を提示しています。
現在、ロンドンのElectric Ballroomを含むバンド史上最大規模のUK/EUツアーを敢行中の彼らは、このシングルによって世界的なファンベースをさらに拡大させています。子供の頃に憧れた「大人」という存在の重圧と、自由だった日々への憧憬。その葛藤を温かくも切ないグルーヴで包み込んだ「Coal Dust」は、急速に進化を続けるRum Jungleの底知れない深みを証明する、極めてパーソナルなアンセムと言えるでしょう。
El Ten Eleven、結成23年目の深化。加速する時代の不安を射抜く新作『Nowhere Faster』を発表。新曲「Uncanny Valley Girl」で描くAI時代のパラノイア。
LA発のポストロック・デュオEl Ten Elevenが、通算16枚目のアルバム『Nowhere Faster』をリリースします。23年のキャリアで最も長い活動休止期間(実際には制作に没頭していた期間)を経て生まれた本作は、目的地不明のまま加速し続ける現代の「速度」への違和感や、人生の不条理な集積をテーマに据えています。今回初めて本物のストリングスやピアノを導入し、これまで以上に重層的で深みのあるサウンドパレットを展開しています。
先行シングル「Uncanny Valley Girl」は、AI時代のパラノイアを冷徹に見つめた楽曲です。長年封印していたディレイ・ペダルを復活させ、濃密なベースの壁を築き上げる一方で、Tim FogartyのタイトなドラムがSF的な不安感に確かな輪郭を与えています。また、アルバムの前半(サイドA)をエレキベース、後半(サイドB)をペダル加工したアコースティックベースで構成するなど、楽器の質感を通じて感情の重みを変化させる実験的な試みもなされています。
アルバムの終盤では、カート・ヴォネガットの小説『スローターハウス5』から着想を得た「So It Goes」などが収録され、加齢や喪失、有限な人生への向き合い方が描かれています。フレットレス・ベースにカポタストを巻くといった奇妙な音響実験を経て辿り着いたアメリカーナ風の哀歌は、加速を止めた瞬間に訪れる内省の時間を象徴しています。足元の地面が揺らぎ始めたとき、何を聴き、何に合わせて踊るのかを問いかける、彼らの集大成とも言える一作です。
Green-Houseの最新作『Hinterlands』がGhostlyより登場。細野晴臣やFFの要素を織り交ぜ、バイオミミクリーを掲げた重層的な音響で、自然と調和する理想郷を描く。
Olive ArdizoniとMichael FlanaganによるデュオGreen-Houseが、新天地Ghostly Internationalから3枚目となるアルバム『Hinterlands』を3月にリリースします。2025年のロサンゼルス山火事という過酷な環境下で制作された本作は、単なるアンビエントの枠を超え、IDMや現代音楽の要素を飲み込んだ重層的な仕上がり。環境不安や政治的な閉塞感が漂う時代において、あえて「幸福」や「喜び」という感情を肯定し、ユートピア的な理想を共有するための道具として、極めて誠実でラジカルな音楽を提示しています。
先行シングル「Farewell, Little Island」は、テクノロジーによって沈む村を描いたアニメ映画から着想を得ており、軽やかなギターサンプルが静かな美しさと悲劇の絶妙なバランスを保っています。アルバム全体では、細野晴臣の『パシフィック』を彷彿とさせる「Sun Dogs」や、ファイナルファンタジーの音楽(特にチョコボの記憶)へのオマージュを感じさせる「Valley of Blue」など、多彩な影響源が螺旋状に絡み合っています。彼らが提唱する「バイオミミクリー(生物模倣)」の概念が、オーケストラのような壮大な響きとなって結実しました。
ビジュアル面では、ヨセミテ国立公園などで撮影した風景を水滴越しに拡大したマクロ写真のアートワークを採用。これは、有機的な自然とデジタルな音響工作が交錯する彼らの音楽的な小宇宙(マイクロコスモス)を象徴しています。サニベル島での幼少期の記憶から山々の広大な景色まで、リスナーを空想の旅へと誘う本作は、驚異の念の裏にある深い憂慮さえも慈しみ、音楽によって自然界との繋がりを再生させようとする彼らの揺るぎない信念の証明です。
DehdのJason Balla、ソロ・プロジェクトAccessoryを本格始動。亡き母のピアノで綴るデビュー作『Dust』
シカゴのインディー・ロック・バンドDehdのメンバーとして活躍するJason Ballaが、ソロ・プロジェクトAccessory(アクセサリ)としてのデビュー・アルバム『Dust』を4月にリリースすることを発表しました。これまで「Wherever You Are Tonight」などのシングルを単発で発表してきましたが、ついにフルレングスの作品として結実します。本作の多くは、亡き母から譲り受け、数年間保管されていたピアノを用いて作曲され、彼のホームスタジオでレコーディングされました。
先行シングルとして公開された「Calcium」は、混迷を極める現代社会への深い洞察から生まれた楽曲です。Ballaは、ニュースから流れる苦しみや憎しみが日常の背景となっている現状に「真の絶望」を感じていた時期にこの曲を書いたと語っています。降り積もる瓦礫のような出来事の中に何らかの秩序を見出し、意味を与えようと葛藤する内面が、繊細なサウンドを通じて描き出されています。
Dehdで見せるエネルギッシュな側面とは対照的に、Accessoryではよりパーソナルで内省的な世界観が展開されています。母のピアノという極めて私的なルーツに触れながら、燃え盛る世界の中で「生きること」を問い直す本作は、Ballaのソングライターとしての新たな深化を証明しています。静かな冬の夜に寄り添うような温かさと、現代的な憂鬱が同居する、美しくも切実なインディー・フォーク作品となりそうです。
LB aka LABAT & Skin On Skin – “Feel So Good Around U”
LB aka LABATとSkin On Skinによるコラボレーション・シングル「Feel So Good Around U」は、現代のダンスミュージック・シーンを牽引する二人のプロデューサーが、その独自のエネルギーを衝突させたフロア・アンセムです。LB aka LABATが得意とする中毒性の高いグルーヴと、Skin On Skinのトレードマークである無骨で破壊力のあるドリル・サウンドやハウスの要素が融合。シンプルながらも強烈なフックを持つボーカル・サンプルが、聴き手を一気に高揚感の渦へと引き込みます。
本作の魅力は、どこか懐かしさを感じさせるレイヴの質感と、最先端のサウンド・デザインが共存している点にあります。「君のそばにいると最高に気分がいい」というタイトル通りのポジティブなヴァイブスを放ちながらも、その奥底には深夜のフロアを揺らすタフでエッジの効いたリズムが貫かれています。互いの強みを最大限に引き出し合ったこのトラックは、クラブ・シーンの連帯感を象徴するような、2026年のダンス・アンセムとして圧倒的な存在感を放っています。
ファッション界も注目する鬼才、Lauren Auderが放つ最新アルバム。スプリングスティーンからミニマリズムまでを飲み込む圧倒的世界観
音楽とファッションの両界でカリスマ的な存在感を放つマルチクリエイター、Lauren Auderが、3月27日にニューアルバム『Whole World As Vigil』をuntitled (recs)よりリリースします。これまでにVegyn、Danny L Harle、Caroline Polachekといった最前線のプロデューサーたちと共作し、モデルとしてもGucciやCelineなどの世界的メゾンと歩んできた彼女。2023年のデビュー作に続く本作は、昨年末に公開されたマッドチェスター風のシングル「yes」に続き、彼女のさらなる進化を告げる待望のプロジェクトです。
現在公開中の新シングル「Praxis」は、インダストリアルなノイズと彼女特有のポップな感性が均衡を保つ、怒涛のサウンドが特徴です。特筆すべきは、金属を切り裂く電動ドリル音のサンプルを楽曲の核に据えている点です。彼女はこの「止まることのない動き」を、自らの哲学である「前進し続けることこそが生きる理由になる」という信念に重ね合わせ、眩い光と轟くような闇が入り混じるエモーショナルな楽曲へと昇華させました。
音楽的なインスピレーション源として、ミニマリズムの巨匠Steve Reich、独創的なポップアイコンKate Bush、そしてBruce Springsteenの名を挙げており、これら一見異質な世界をLauren Auderというフィルターを通して唯一無二の形へと統合しています。緻密に構成された音像と力強いメッセージが同居する本作は、現代の音楽シーンにおける彼女の重要性を改めて証明する、記念碑的なアルバムとなるでしょう。
エモ、マスロック、そして狂気。Love Rarelyが新曲「Will」で提示する、トラウマを凌駕する圧倒的カタルシス
リーズのオルタナティブ・シーンから登場したLove Rarelyが、待望のデビューフルアルバム『Pain Travels』を今春リリースします。本作は、エモ、ポストハードコア、マスロックの境界線を縦横無尽に駆け抜ける野心作。ギターのLew Taylor自らがプロデュースを手がけ、寝室や即席の録音スペースで1年をかけて制作されました。家族のトラウマや機能不全な家庭、そして過去の傷に縛られずに大人へと成長していく葛藤を、恐れを知らない剥き出しの感情で描き出しています。
サウンド面では、複雑な変拍子やプログレッシブな構成、さらにはラジオで即通用するようなキャッチーなフックと、突発的に爆発するヘヴィネスが同居する圧倒的な密度を誇ります。アルバムの幕開けを飾る新曲「Will」は、まさにその「全部盛り」な彼らのスタイルを象徴する一曲。Alex Dixonが監督したビデオでは、ボーカルのCourtney Levittが矢を射られ、口紅まみれになるという衝撃的なビジュアルを通じて、楽曲の持つ混沌と美しさが表現されています。
また、本作は「脳を抉る」ほど強烈なインパクトを与えるカバーアートも大きな話題を呼んでいます。すでにCallous Daoboysとのツアーも決定しており、2026年のUKロックシーンにおいて無視できない存在感を放っています。これまでに発表された人気シングル「Disappear」なども収録された本作は、単なる音楽作品を超え、傷跡を力強い自己定義へと変えていくバンドの魂の証明と言えるでしょう。