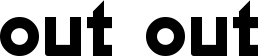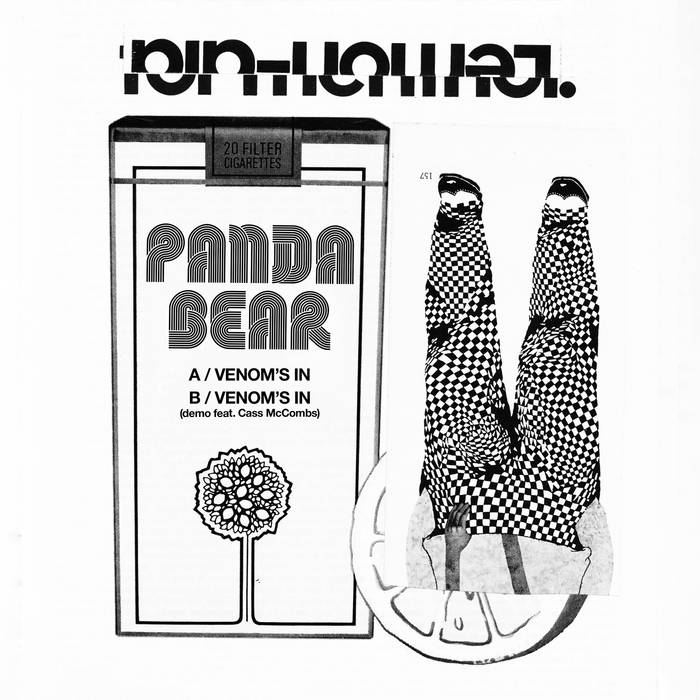Gut Model – “Windmills”
ベルギーのモンス出身、現在はブリュッセルを拠点に活動する4人組バンド Gut Model(Simon Francois, Leonard Thiebaut, Lucas Roger, Paul Brynaert)が、EXAG’ Recordsよりニューシングル「Windmills」をリリースしました。2020年の結成当初、文化的に制限された故郷から離れ、首都での共同生活の中で生まれた彼らの楽曲は、大衆的なお祭りへのノスタルジーと解放的な野心を内包しています。カセットコンピレーションへの参加やシングル「New Tattoo」の発表を経て、ライブプロジェクトとしての地位を確立した彼らは、満を持して新アルバムの制作に取り掛かりました。
新作のレコーディングは、一切の妥協を排したクリエイティブな親密さを守るため、彼ら自身のリハーサルスタジオで行われました。音楽的には、身近なシーンからインターネット上の無名の発見まで幅広く影響を受けており、昨今のポストパンク・リバイバルに対しては「嫌気がさすほど聴き込んだ」という批評的な視点も持ち合わせています。この野心的なプロジェクトは、B.U.N.Kプロジェクトの立ち上げを通じてEXAG’ Recordsとの契約へと結実しました。
Big Harp – “Boys Don’t Cry”
Big Harp(Chris SenseneyとStefanie Drootin-Senseneyによるデュオ)が、The Cureのカバー曲「Boys Don’t Cry」を携えて帰還しました。これは彼らにとって10年ぶりの新作であり、初期の名作『White Hat』や『Chain Letters』を輩出した古巣 Saddle Creekからの久々のリリースとなります。Bright EyesやThe Good Lifeでの活動でも知られる二人は、2010年の結成直後にわずか1週間の練習でデビュー作を録音したという逸話を持ちますが、長年のツアーを経て、そのサウンドは初期のローファイなフォーク・ロックから、よりエネルギッシュで荒々しいものへと進化を遂げてきました。
今回のリリースは、ティーンエイジャーになった彼らの娘がThe Cureに夢中になったことがきっかけで生まれました。オリジナルへの敬意を払いつつも、現在の彼らはオーバーダブやサポートメンバーを一切排した「純粋な二人編成」での演奏にこだわっています。「Boys Don’t Cry」の無駄のない完璧な構造は、余白を活かしてメロディと歌詞を際立たせる彼らの現在のアプローチに合致しました。普遍的で強固な楽曲の核を掘り起こそうとするこの試みは、彼ら自身が自らの楽曲制作において常に追求している理想の姿を反映しています。
Panda Bear and Cass McCombs – “Venom’s In”
Panda Bear(Noah Lennox)が、2025年の最新アルバム『Sinister Grift』に収録されている楽曲「Venom’s In」を、Record Store Day 2025限定のシングルとしてリリースしました。この作品は、アルバム本編でも重要な役割を果たしている盟友Cass McCombsとのコラボレーションを軸にした特別なパッケージとなっています。
本シングルには、アルバムに収録された完成版の「Venom’s In」に加え、Cass McCombsによる同曲のデモ・バージョンがカップリングされています。同じ楽曲が二人の異なるアーティストの感性を経てどのように形作られたのか、その創作プロセスや親密な音楽的対話を垣間見ることができる、ファンにとって非常に貴重な資料的価値の高い一枚です。
Market(Nate Mendelsohn)が放つ2026年の最重要作『Cleanliness 2: Gorgeous Technologies』:アヴァント・ポップと現代ラップの美学が交差する、現代人の狂騒的な思考を鏡のように映し出した音響のスペクタクル
Market(Nate Mendelsohn)が2026年2月27日に発表する5作目のアルバム『Cleanliness 2: Gorgeous Technologies』は、現代人のめまぐるしい思考を映し出した、極めてパーソナルな音楽言語の到達点です。Phil ElverumやVan Dyke Parksに通じる前衛的な構造に、現代ラップやR&Bの質感を融合させた本作は、Rose Droll(Feist)が客演した「CHURCH」に象徴されるように、Michael Haldeman (Dijon) や Justin Felton (L’Rain, Big Thief) といった豪華な協力者を「劇中劇」の助演キャストとして配した、濃密な一人芝居の様相を呈しています。
楽曲群は、新旧のテクノロジーを駆使した歪な電気音響デザインによって形作られています。隣人の叫び声という日常の一幕をオートチューン越しに切実な内省へと変える「NEIGHBOR」や、トラップ風の高速な韻律(フロー)で毒性のある元恋人との関係を歌う「40 YEARS」など、シングル曲においてもその独創性は際立っています。特に、明確な拍子を排した「FUCK FAMOUS PEOPLE」では、セラピーについての会話調の独白が、フリージャズ風のドラムや天上の合唱へと変貌し、Frank Oceanを彷彿とさせるパラソーシャルな関係(疑似親密関係)への告発へと繋がります。
アルバムの核心にあるのは、デジタルで劣化したiPhoneの写真や家族とのFaceTimeといった「ミレニアル世代のプルースト的ムードボード」であり、過去と断片化された現代を繋ごうとする孤独な試みです。最終曲「THE GROCERIES」で「論理は無視する、僕には華やかなテクノロジー(gorgeous technologies)があるだけだから」とサックスのサンプリングに乗せて歌うように、Mendelsohnは矛盾に満ちた自分自身を肯定し、個人主義の価値を訴えます。めまぐるしい日常の中で、アクション満載の3分間の楽曲を通して、能動的な聴取と深い内省を促すシンフォニックな傑作です。
more eazeことmari rubio、多忙を極めた2025年を経て放つ新作『sentence structure in the country』を発表:伝統的フォークのルーツを現代的なグリッチ・ミュージックへと昇華した野心作
テキサス出身のマルチインストゥルメンタリスト、more eazeことmari rubioにとって、2025年は多忙を極める一年となりました。Lynn AveryとのユニットPink Mustの始動や、claire rousayとの共作EP『no floor』、さらにGrumpyやFriendshipとのコラボレーションなど、休むことなく活動を続けてきました。その勢いは来年にも引き継がれ、彼女のルーツである伝統的なフォークやカントリー音楽を、近年の特徴である霞がかったグリッチ・ミュージックへと統合したソロアルバム『sentence structure in the country』がリリースされます。
このニューアルバムには、Wendy EisenbergやRyan Sawyerといった即興演奏界の精鋭たちが参加しています。先行シングル「bad friend」は、これらの多様な音楽世界が静かに、かつ親密に調和することを示した一曲です。rubioによれば、この曲は長年彼女の中にありましたが、Alan Sparhawkeとのシカゴ公演で演奏したことが再考のきっかけとなりました。伝統的な奏法に縛られず、ギターのようにかき鳴らされるペダル・スティールと、独自のエレクトロニクス設定が、楽曲のユニークな構造を解き明かす鍵となっています。
歌詞の面では、「友人に対して抱いてはいけないはずの恋愛感情」や、人とうまく付き合えず自分を「エイリアン」のように感じてしまう孤独感が描かれています。特に、テキサスで過ごした最後の数年間の対人関係における苦悩が反映されており、長年温められ変容し続けてきたこの曲には、彼女の個人的な内省が深く刻まれています。音楽的、そして精神的な「安らぎ」を求めて回帰したこの楽曲は、アルバム全体の方向性を象徴する重要な作品と言えるでしょう。
Doll Spirit Vessel – “Godless”
フィラデルフィアのインディーロックバンド、Doll Spirit Vesselが、2022年のデビューアルバム『What Stays』以来、数年間の沈黙を破って新しいシングル「Godless」をリリースしました。デビュー作で大きな注目を集めた彼女たちにとって、今回の新曲は久しぶりの待望の復帰作となります。
この楽曲では、バンドリーダーのKati Malisonの歌声が、美しいバイオリンの旋律とギターの音色の上を漂うように響きます。そのサウンドは、「もし現代にケイト・ブッシュが23歳で、地下のライブハウス(ベースメント・ショー)で演奏していたら作りそうな音楽」と評されるほど、独創的で魅力的な雰囲気を醸し出しています。
Bill Callahan – “Lonely City”
Bill Callahanの新しいアルバム『My Days Of 58』が新年の数ヶ月後にリリースされる予定です。このインディーズのベテラン・シンガーソングライターは、先行シングル「The Man I’m Supposed To Be」に続いて、本日さらに優れた楽曲「Lonely City」を発表しました。多くのCallahanの楽曲と同様に、「Lonely City」は慎重に構成されていますが、まるで自然発生的に展開しているかのように、のんびりとしたペースで進行します。このゆったりとした即興的な雰囲気は、しばらく離れていた場所と再会するという歌詞の内容に完璧にマッチしており、外の世界への冒険を示唆しながらも、Callahanが本作で求めた「リビングルームの雰囲気」を醸し出しています。
Callahan自身は、「Lonely City」について、「何十年も書こうと思っていた曲」であり、これまで「人間と内なる精神」に焦点を当ててきたため、コンクリートや鉄鋼について書くことは「あり得ない」と感じていたと述べています。しかし、都市も人間によって作られているため人間的であり、「友人と同じように、都市との間には関係性がある」ということを認識する歌だと説明しています。この楽曲のミュージックビデオは、ストリートフォトグラファーのDaniel Arnoldが、彼自身の15年間にわたる写真から構成したものであり、現在視聴可能です。
bobbie – “I Could Call You”
ウェスタンマサチューセッツ出身のアーティスト、bobbieが、Orindal Recordsに加入し、新しいシングル「I Could Call You」をリリースしました。これは彼女の次なるディスコグラフィーの最初の先行シングルとなります。このリリースは、bobbieとレーベルとのコラボレーションの始まりを告げるもので、没入感のある雰囲気と正確なメロディ構造を特徴とする彼女のコンテンポラリーなドリームポップの存在感を強固にしています。
この楽曲は、bobbieがFelix Walworth(Florist、Told Slant)と共同で書き、プロデュースしたもので、オーガニックなパーカッション、シンセサイザー、そして一定のリズムを保つギターが調和する中で、徐々に展開し、コーラスで最高潮に達します。マスタリングはJosh Bonatiが手掛け、楽曲にバランスと明瞭さを与えています。タイトルである「I could call you」というフレーズが最初と最後に登場し、感情的なつながりの永続性を表す物語のサイクルを生み出しています。bobbieは、憂鬱さを内省的な空間へと変える能力をこの曲で示しており、詩的なアプローチと瞑想的なサウンドを通じて、エレクトロニクスとポップな感性を組み合わせた自身のアイデンティティを再確認しています。この新しい作品は、2023年にFlower Soundsから発表された『Rhododendron』や、これまでの自主制作プロジェクトに続くものであり、Orindal Recordsへの参加により、bobbieは創造的な世界観を拡大し、来年発表される新たな楽曲の開発へと進んでいます。
Alice Costelloe – “Anywhere Else”
Alice Costelloe、Moshi Moshi Recordsからデビューアルバム『Move On With The Year』を発表Alice Costelloeが、2026年2月にMoshi Moshi Recordsからリリース予定のデビューアルバム『Move On With The Year』から、ニューシングル「Anywhere Else」を公開しました。このトラックは、彼女の2024年のEP『When It’s The Time』の直後に生まれました。楽曲のプロデュースはMike Lindsayが担当しています。
「抵抗が最も少ない道」を選んだ、自然な創作プロセスCostelloeは、この曲の制作プロセスについて「とても簡単で自然に感じられた」と説明しています。「すべてのリコーダーのメロディは、私が最初に演奏したものであり、何がクールか、他の人が何をしているかを気にすることなく、自分に浮かんだものをそのまま書いているように感じました」と彼女は語ります。彼女は、この「抵抗が最も少ない道」を進むという姿勢を、「サウンドとテーマの両方において、アルバム全体で感じられるようにしたかった」と述べています。
Immaterialize – “Evolution”
シカゴを拠点とするデュオ、Immaterialize(Alana Schachtel /別名 LipsticismとErik Fure /別名 DJ Immaterialから成る)が、デビューアルバム『Perfect』を1月23日にAngel Tapesからリリースします。この度、そのアルバムから最初の、幽玄な先行シングル「Evolution」が発表されました。
デュオは「Evolution」について、自己の中にある意地悪な(醜い)部分を見つめつつも、それだけがすべてではなく、利他主義(そしてまた貪欲さ)への傾向も存在することを認識することからインスピレーションを受けていると述べています。「自分自身が全く別の人であってほしいと願う空間にあまり時間を費やしたくない。自己の中にある感情の全スペクトルを受け入れる」というメッセージが込められています。