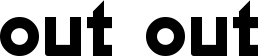keiyaA – “k.i.s.s.”
keiyaAが、セカンドアルバム『hooke’s law』のリリースに先立ち、最新シングル「k.i.s.s.」を発表しました。この曲のミュージックビデオは、keiyaAと共同ディレクターのCaity Arthurによる長年のコラボレーションの第三章にあたります。
ビデオ「k.i.s.s.」では、泡だらけの洗車場を舞台にした想像力豊かなシーンでkeiyaAが主役を務めています。そこでは、誘惑の駆け引きが振り付けへと変化し、90年代後半から2000年代初頭のR&Bクラシックのビデオクリップが持つ活気ある雰囲気とアイロニーを愛情深く想起させつつ、彼女独自のタッチで完全に作り替えられています。
Concrete Husband – “A Calling From Afar”
楽曲「A Calling From Afar」は、当初、ホイットニー美術館で上映される予定だった短編映画のために、即興のスコアとして制作されました。この映画では、Alvin Aileyのダンサーたちが美術館内を舞い、音楽はその動きへのライブな反応として生み出されました。アルペジオ(分散和音)で奏でられるフルートは、郷愁と希望の感覚を漂わせる静かで発展的なハーモニーを描き出します。それはまるで、遠くに光を見るような感覚であり、変化は可能であるという確かな希望と、それに抵抗する力が絶えず存在する葛藤を示唆しています。
音響的に、この曲は夢や記憶の中を漂うかのような、幽玄で捉えどころのないフルートの遠い合唱のように感じられます。楽器がそこにありながらも手の届かない、ノスタルジックな雰囲気が特徴です。徐々にシンセサイザーが加わることで、サウンドはより重厚で決定的な存在感を増し、その変化は、オーケストラの中央に位置するフルート奏者を囲む音の記憶のようです。この荘厳さは、マーラーの交響曲第9番の最終楽章に見られる重厚な叙情性に通じます。DJとしての活動で電子的なテクスチャを取り入れてきたConcrete Husbandにとって、このフルートとシンセの融合は、彼の音楽的旅路における古典と電子という二つの世界の二重性を反映した、希望を抱き続けるための力強い音楽的な呼びかけとなっています。
Vogues – “And Then Nothing/Nevertheless”
Voguesは、コーンウォール出身でロンドンを拠点に活動するミュージシャン兼プロデューサーによるソロプロジェクトです。彼は、キャンプなポップの極大主義(マキシマリズム)とローファイな親密さという視点を通して、アイデンティティ、記憶、感情の過剰さを探求しています。また、バンドThe Golden Dregsでシンセ奏者を務めています。
Voguesは、ホームメイドな質感と豪華なアレンジメントを融合させ、「Arthur RussellからAnohniに至るクィアな偉人たちを想起させる」音楽を作り上げています。彼の音楽は、クィアな欲望と自己の再創造という個人的な領域を描き出し、新作シングル「And Then Nothing/Nevertheless」をJoy of Life Internationalからリリースしました。
Sugarbeets – “Déjame En Paz”
楽曲「Déjame en paz」は、失恋と、同じパターンを繰り返す関係性の循環からインスピレーションを受けて制作されました。曲の冒頭の歌詞は、関係性における甘い言葉を思い起こさせますが、それがやがて意味をなさなくなったという気付きへと続きます。物語は、一度は別れを決断した元恋人が、その決意を貫けずに許しを請うという展開を辿ります。
タイトルである「Déjame en paz」は「私を放っておいて」または「一人にして」という意味を持ち、エピファニー(悟り)に至った心境を体現しています。この曲は、時には相手に自分を解放してもらうために、自らその人を手放す必要があるという理解を描いています。これは、過去の循環を終わらせるために、自分自身がエンパワーメント(力を得た感覚)を感じることへの心からのトリビュート(賛歌)となっています。
「大人の役割を現実にしてはならない」:Boys Lifeが約30年ぶりの新作EP『Ordinary Wars』から「Always」を公開、若々しいエネルギーと宇宙的視点を提唱
Boys Lifeは、Spartan Recordsとの共同で、11月21日にリリースされる新作4曲入りEP『Ordinary Wars』から最新シングル「Always」を発表しました。この曲は、全ての人間に若々しいエネルギーと存在感を持ち続けるよう促すメッセージであり、大人の役割が現実になってしまうことを許すべきではないと示唆しています。ボーカルのBrandon Butlerは、Ram Dassの言葉を引用し、「私たちは誰でもない者として始まり、誰でもない者になる。その中間は驚き、発見、そして祝賀であるべきだ」と語り、人生を子供が喜びに満ちたものに接するように扱うべきだと提唱しています。この曲とアルバムは、「名前や肩書き、エゴではなく、私たちは具現化された宇宙である」というバンドの深遠な視点を反映しています。
『Ordinary Wars』は、カンザスシティのインディーロック・カルテットBoys Lifeにとって約30年ぶりとなるオリジナル作品で、彼らのクラフトへの揺るぎない献身を示しています。1993年にミズーリ州カンザスシティで結成された彼らは、情熱的で不協和音を伴うギター主導のサウンドとDIY精神、ミッドウェスト特有の感性で知られ、KnapsackやGiant’s Chairなどと同時代に活動し、ミッドウェスト・エモ・シーンの不可欠な一部となりました。1997年の解散後もメンバーは個々の音楽活動を続けましたが、2015年と2024年の再結成ツアーがきっかけとなり、彼らの共同作業の精神が再燃しました。
この新作EPは、2024年6月に長年の協力者であるDuane Trowerと共にWeights and Measures Soundlabでライブレコーディングされ、彼らの原点を思わせる環境で集中的に制作されました。『Ordinary Wars』は、死すべき運命、社会の幻滅、そして目的のある存在の切迫性といったテーマを掘り下げています。Butlerは、「私たちの世界、特に私たちの国は、失敗した実験だと見ている。私たちは時間を無駄にしている」と述べ、リスナーに無意味な追求を避けるよう強く促しています。ドラムのJohn Andersonは、レコーディング体験を「深く意味のあるもの」と要約し、「Bleeds」や「Equal in Measure」などのトラックがスタジオジャムから自然発生的に生まれたことで、彼らの新たな相乗効果が即座に捉えられています。
Together PangeaがThe Red Pearsをフィーチャーした新曲「Halloween」を公開:サーフ・サウンドに「Deftones」の影響を加え、20代の不安をダークな自信に変えた『Eat Myself』
ロサンゼルスのバンド、Together Pangeaは、2026年1月16日にニューアルバム『Eat Myself』をリリースします。このトリオ(William Keegan、Danny Bengston、Erik Jimenez)は、これまでのガレージロックやサーフ・ルーツをさらに拡張し、Deftones、Smashing Pumpkins、My Bloody Valentineなどにインスパイアされた新しいサウンドを探求しています。これまでに「Like Your Father」、「Empty Church」、「Little Demon」、「Molly Said」が公開されており、10月24日にはThe Red Pearsをフィーチャーした新シングル「Halloween」を公開しました。この「Halloween」は、プロデューサーのMikey Freedom Hart(Taylor Swiftなどを手がける)によるもので、タイトルに反して音響的にはそれほど不気味ではないものの、彼ららしいサーフ調のサウンドと、「この悲しみが怒りだったらよかったのに/そうすれば僕は詩人になって、とっくに死んでいただろう」といった巧妙で遊び心のある歌詞が特徴です。
グラミー賞を3度受賞したプロデューサー、Mikey Freedom Hartと共に制作された『Eat Myself』は、Together Pangeaにとって大胆な新時代の幕開けとなります。彼らは20代の落ち着きのない不安を、経験と成長によって培われたよりダークで穏やかな自信へと交換しました。バンドは、『Jelly Jam』(2010年)や『Badillac』(2014年)など、作品を重ねるごとに音楽の境界を押し広げてきた実績があります。これまで数百万回のストリーミング再生を記録し、Rolling StoneやPitchforkなどの主要メディアから高い評価を獲得、Jimmy Eat WorldやFIDLARらともツアーを行うなど、インディーロックシーンで重要な役割を果たし続けています。
キャリアが15年を超えた今も、Together Pangeaは進化を続け、これまで以上に重要な存在感を示しています。2025年は、Coachellaでの待望のデビューや、ロサンゼルスのThe El Reyでのキャリア史上最大規模の公演といった大きな節目を迎えました。彼らは、11月にはサンフランシスコやサクラメントを含むカリフォルニアでの短期ヘッドライン公演を、そして1月にはロサンゼルスでのレコードリリース記念公演を含む一連の公演を行う予定です。新作『Eat Myself』は、彼らの揺るぎない音楽への献身と成長の証となっています。
Animal Collectiveで唯一の未経験者 Geologist、ついにソロ・デビューへ!SST Recordsと日本の実験音楽に捧ぐ:ギターを諦めハーディ・ガーディを選択した制作秘話を語る—先行シングル「Tonic」はKeiji Hainoへのオマージュ
Animal Collectiveのメンバーの中で唯一ソロ・アルバムをリリースしていなかったGeologist(ブライアン・ワイツ)が、ついにその沈黙を破り、来年1月30日にDrag Cityから初のソロ・アルバム『Can I Get A Pack Of Camel Lights?』を発表します。この待望の作品には、バンドメイトのAvey Tareをはじめ、ドラマーのEmma Garau、Alianna Kalaba(FACS, Cat Power)、Ryan Oslance(The Dead Tongues, Indigo De Souza)、さらにはShamのShane McCord(クラリネット)やMikey Powers(チェロ)など、豪華なミュージシャンが参加しています。
アルバムは、独特な弦楽器であるハーディ・ガーディと、伝説的なパンク・レーベルSST Recordsから大きなインスピレーションを受けています。Geologistは、「10代の音楽はギターが中心だったが、自分はギターが苦手だった」と語ります。彼は、Keiji Hainoのハーディ・ガーディの演奏に感銘を受けつつも、その域に達するのは難しいと感じ、SSTのGreg Ginnがドラムマシンに合わせてギターソロを演奏したという逸話にならい、ハーディ・ガーディでこのアルバムを制作しました。ハーディ・ガーディという楽器が、彼を「お気に入りのミュージシャン」のスタイルに近づけてくれたと述べています。
このアルバムからの最初のシングルとして「Tonic」が公開されました。このタイトルの由来は、Geologistが1998年にJohn Zornの惜しまれつつ閉店したクラブで目撃した、Keiji Hainoの伝説的なライブセットに敬意を表したものです。
古代の儀式と未来的テロルの衝突:UK-US実験的ブラックメタル・トリオ Qasu、デビュー作『A Bleak King Cometh』で「古代未来ブラックメタル」の概念を確立
UKとUSを拠点とする実験的ブラックメタル・トリオ、Qasuが、デビュー・アルバム『A Bleak King Cometh』をPhantom LimbとApocalyptic Witchcraftの共同リリースで2026年1月30日に発表します。バンドが「古代未来ブラックメタル」と称するそのサウンドは、ブラックンド・サイケデリア、オカルト・テクノ、歪んだサウンドデザインを融合させた、圧倒的かつ異世界のヴィジョンを提示しています。既知のバンドのメンバーによって結成された彼らのデビュー作は、破滅的なリフと猛烈なブラストビート、そして苦悶に満ちたヴォーカルを特徴とし、エクストリーム・メタル界に類を見ない作品として期待されています。
アルバムから先行リリースされたリード・シングル「Jewels Where The Eyes Once Were」は、Qasuの実験的なアプローチを明確に示しています。この曲は、ニューウェーブ・シンセ、激しいテクノのキックドラム、フィールドレコーディング、そして太鼓のパーカッションを、終末的なギターワークと組み合わせています。ヴォーカリスト兼エレクトロニクス・プログラマーのRahsaan Saganは、「Bring me a living heart… to deify the bleak king」といった悪夢のような叫びで音楽を牽引し、スペクトル合成とビート駆動の推進力でブラックメタルの音域を未踏の領域に拡大しています。
Qasuの「古代未来ブラックメタル」という世界観は、魔女狩りや異端の儀式といった古代のモチーフと、エイリアンの通信やスターゲイトといったパレオ・フューチャリズム的SF要素が衝突することで成り立っています。ドラマーのNikhil Talwalkar(Anal Stabwound)がその宇宙的な広がりを物理的な強度で地面に留める一方、インストゥルメンタリストのAldous Danikenは、アルバム・タイトルを「人類史における暗黒時代」への言及としています。UKとUSを股にかけるリモートでの共同制作を通じて、DanikenがSaganとTalwalkarの貢献を自身のスタジオで集めて完成させた『A Bleak King Cometh』は、彼らの破壊的で、強大だが、最終的に守護的なゴーストからインスピレーションを受けた名前を持つ、Qasu初のフル・リリースです。
The Twilight Sad – “WAITING FOR THE PHONE CALL”
スコットランドのロック・バンド、The Twilight Sadが、待望のカムバックを果たし、新作シングル「Waiting For The Phone Call」をリリースしました。この楽曲は、なんとThe Cureのフロントマン、Robert Smithをフィーチャーしており、内省的でありながらも強烈なサウンドが特徴です。さらに、バンドは2026年のUKおよびヨーロッパでのヘッドラインツアー開催も発表しました。現在のメンバーは、フロントマンのJames GrahamとギタリストのAndy MacFarlaneの二人となっています。
The Twilight SadとRobert Smithの関係は長年にわたり深く、The Cureの世界ツアーのサポートを務めるなど、密接な交流があります。Smithはかつて彼らを「一貫して素晴らしく、感情的で、強烈で、刺激的で、面白い、最高の曲を演奏する最高のバンド」と絶賛していました。今回Smithが参加した新曲は、「決してかかってきてほしくない電話」を詳細に描いた自伝的な壮大な曲と評されており、ファン待望の復帰作となっています。彼らは来年の夏にも、The CureのUKおよびヨーロッパでの大規模な野外公演に再び参加する予定です。
Pan Amsterdam – “KIMCHI” (feat. GUTS)
ラッパー/トランペッターのPan Amsterdam がリリースしたシングルが「KIMCHI (Feat. GUTS)」です。この楽曲は、ユニークで知的なリリックとジャズの要素を取り入れたヒップホップ・サウンドで知られるPan Amsterdamと、フランスの著名なプロデューサーであるGUTS(ガッツ)がコラボレーションした一曲です。このシングルは、2025年10月28日に最新リリースとして確認されています。
このシングルは、Pan Amsterdamの特徴的なウィットに富んだ言葉遊びと、GUTSによるソウルフルでグルーヴィーなプロダクションが組み合わさることで、リスナーに鮮烈な印象を与えます。二人のアーティストの個性がぶつかり合い、ヒップホップでありながらもジャンルの垣根を超えた、洗練されたサウンドを生み出しており、Pan Amsterdamの音楽カタログにおける注目すべき追加作品となっています。