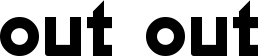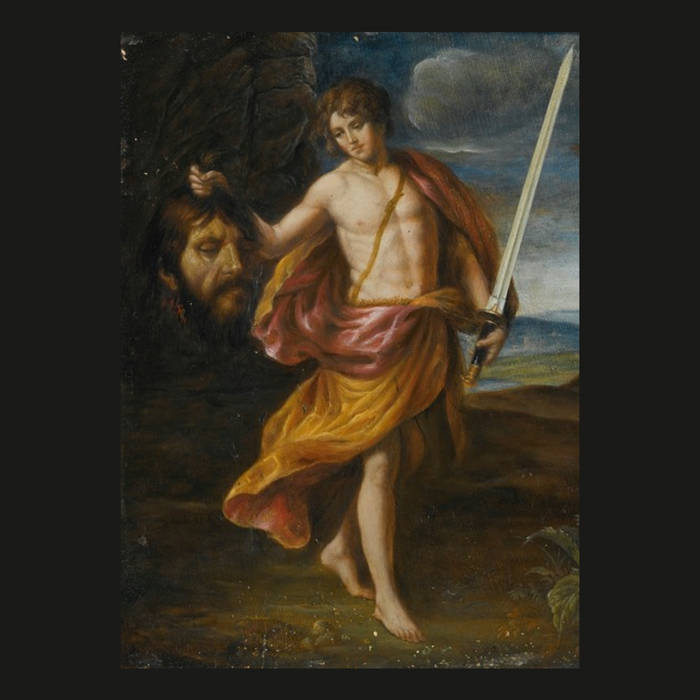シカゴを拠点とするエモ/グランジ・バンド Footballhead が、新曲「Diversion」を公開しました。昨今の音楽シーンでは、Deftones 流の重厚なギターリフと繊細なヴォーカルを組み合わせた若手バンドが増えていますが、彼らはそのスタイルをさらに推し進めています。新作ビデオは高校の体育館のような場所で撮影され、フロントマンの Ryan Nolen が巨大なジーンズを履きこなすなど、90年代後半のオルタナティブ・ロックの空気を完璧に再現しています。
ニューアルバム『Weight Of The Truth』からの最新シングルである本作は、推進力のあるリフが特徴的な一曲です。監督の Tom Conway と Chris Owsiany が手掛けたビデオも含め、もし彼らをタイムマシンに乗せて1998年のロック・フェスティバルのサブステージに出演させたとしても、全く違和感がないほどの徹底した世界観を持っています。当時のサウンドに思い入れのある世代にはたまらない、ノスタルジーと新鮮さが共存する仕上がりです。