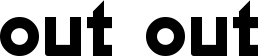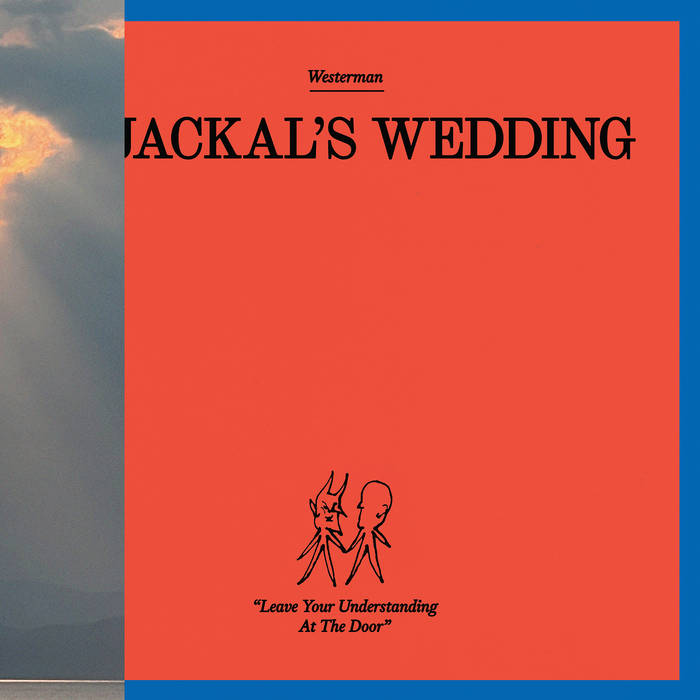楽曲「A Calling From Afar」は、当初、ホイットニー美術館で上映される予定だった短編映画のために、即興のスコアとして制作されました。この映画では、Alvin Aileyのダンサーたちが美術館内を舞い、音楽はその動きへのライブな反応として生み出されました。アルペジオ(分散和音)で奏でられるフルートは、郷愁と希望の感覚を漂わせる静かで発展的なハーモニーを描き出します。それはまるで、遠くに光を見るような感覚であり、変化は可能であるという確かな希望と、それに抵抗する力が絶えず存在する葛藤を示唆しています。
音響的に、この曲は夢や記憶の中を漂うかのような、幽玄で捉えどころのないフルートの遠い合唱のように感じられます。楽器がそこにありながらも手の届かない、ノスタルジックな雰囲気が特徴です。徐々にシンセサイザーが加わることで、サウンドはより重厚で決定的な存在感を増し、その変化は、オーケストラの中央に位置するフルート奏者を囲む音の記憶のようです。この荘厳さは、マーラーの交響曲第9番の最終楽章に見られる重厚な叙情性に通じます。DJとしての活動で電子的なテクスチャを取り入れてきたConcrete Husbandにとって、このフルートとシンセの融合は、彼の音楽的旅路における古典と電子という二つの世界の二重性を反映した、希望を抱き続けるための力強い音楽的な呼びかけとなっています。