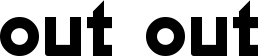ARTIST : The Bug Club
TITLE : Very Human Features
LABEL : Sub Pop Records
RELEASE : 6/13/2025
GENRE : indierock, rock
LOCATION : Wales, UK
TRACKLISTING :
1. Full Grown Man
2. Twirling in the Middle
3. Jealous Boy
4. Young Reader
5. Beep Boop Computers
6. Muck (Very Human Features)
7. When the Little Choo Choo Train Toots His Little Horn
8. How to Be a Confidante
9. Living in the Future
10. Tales of a Visionary Teller
11. The Sound of Communism
12. Blame Me
13. Appropriate Emotions
The Bug Club、再びガレージロック市場に登場、またもや血統書付きレコードを売りさばく。
4枚目のLP『Very Human Features』が6月13日に発売される。この作品は、バンド初のSub Popからのリリースとなった2024年の『On the Intricate Inner Workings of the System』に続くものだ。前作では、バンドはBBC Radio 6との相思相愛を続け、KEXPでのセッションのおかげで新たな恋を始め、NMEの誌面にも登場した。バケットリストの他の項目は?ああ、そうだ、ホームグラウンドであるGreen Man’s Walled Gardenを、存在しない天井まで満員にしたフェスティバルの出演もあった。そして、私たちイギリス人が噂には聞くものの、実際にはなかなか行くことのないアメリカの会場でのショー。このレコードは、バンドに終わりのないツアーを続け、このバンドの絶え間ないレコードリリースという快進撃のおかげで肥大化し、期待に胸を膨らませた熱狂的なファンに餌を与える口実を与えてくれる。典型的な遊び心にあふれ、リフ満載でスマートなBug Club Tunesの新バッチだ。
しかし、まずは単独シングルから。なぜなら、それがこのバンドのやり方だからだ。「ウェールズに行ったことはあるかい?」とバンドは「Have U Ever Been 2 Wales」で問いかける。もし行ったことがないなら、なぜ行かないんだ?いいところだよ。もし彼らがすでにまともなハーモニーの国歌を持っていなかったら、新しい不協和音の国歌になるだろう。ああ、国民的プライドが嫌な奴の印以外の何かである国出身でありたいものだ。古典的なチャグ・アロングとして始まり、エイリアンの聖歌隊のようなものに邪魔され、その後彼らは爆発する。観光局で働いているDinosaur Jr.を思い浮かべてほしい。そしてウェールズ風。間違いなくウェールズ風だ。
個人的には、興味のない個人的な意見が、例えばバンドの略歴など、必要のない場所に挿入され、つまらない個人的な意見が垂れ流されるのが嫌いだ。おそらく、だからこそ、この作品はうまくいくのだろう。ありがたいことに、『Very Human Features』でThe Bug Clubは、集合的な精神として提示するという彼らの習慣を続けている。二人で一人。このような特異で共有された視点、ユーモアのセンス、ポップなメロディーのコツを持つ二つの創造的な力を持つバンドはめったにない。「Beep Boop Computers」では、ボーカルのSam(ギターも担当)とTilly(ベース担当)が、「私」と「私たち」を区別なく交換し、その一方で、アルバムのタイトルが言及している人間的な側面を華麗なグラムロックで解体しながら、人間関係や経験を突き刺している。話題を変えずに、「How to Be a Confidante」は、The Bug Clubが本当に得意とすること、つまり、再び同じ心から発せられる二つの声として話し、私たちが皆どのように生きているかの共通の側面を摘み取り、それを馬鹿げたものに聞こえさせることを行っている。シュールなものは、身近なものを無視することではなく、身近なものの中にある。The Bug Clubはそれを知っており、その理解が、このガレージ風の傑作のバックボーンを形成する容赦のないベースラインと結びついている。
身近なものをからかうことで、2曲目までにユーモアが内向きになり、The Bug Club自身が攻撃の対象になっているのは驚くことではない。「Twirling in the Middle」では、空港をゴミだらけにするスパイ小説家のAndy McNabと聖書の共同執筆者の両方を侮辱するために寄り道した後、SamとTillyは「これが終わりだと思ったかい?私たちはまだ始まったばかりだよ」と歌う。おそらく彼らの多作なアウトプットへの言及だろうか。結局のところ、これは2022年以降4枚目のLPであり、すべてのEPや単独の雑多な作品は言うまでもない。それから彼らは、テンポチェンジ(「ロックステディをやっているのか?」)に眉をひそめ、「これが終わる準備ができたところで、ソロを始めるよ」と付け加え、まさにその通りにするという、ハラキリスタイルのナイフをさらに突き刺す。そして、それは本格的なソロだ。常にそうだ。それは、The Bug Clubがやっていることの正体を解き明かすジェットコースターであり、同時に、以前のアルバムで成し遂げられた作品を土台とし、互いに積み重ねられた創造性の層を私たちに提示している。
SamとTillyの組み合わせ。それには名前がある。そして、彼らが冗談を言っていることを考えると、彼らがそうかもしれないと思うのは魅力的だ。しかし、The Bug Clubの多次元的な性質こそが、『Very Human Features』を彼らの以前の作品と同じように何度も聴きたくなるものにしている。「Jealous Boy」「Appropriate Emotions」「Muck (Very Human Features)」は、すべてLPにさらに痛烈なトーンを与えている。最初の曲は、期待と比較に取り組み、フラストレーションと怒りにおいて避けられない浮き沈みと爆発を反映したラウド・クワイエット・ラウドの構成になっている。「Appropriate Emotions」は、その歌い手を可能な限り人間の経験からかけ離れたように聞こえさせながら、深く共感できるようにしている。おそらく、それが共感できる理由だろう。そして「Muck (Very Human Features)」は、アルバム2の『Rare Birds: Hour of Song』のフォーク調でスポークンワードの要素を組み合わせ、自分の世界の居場所について熟考している。
当初、Sam Willmett(ボーカル/ギター)とTilly Harris(ボーカル/ベース)、そしてDan Matthew(ドラム)のソングライティングの中核で構成されていたThe Bug Clubは、2016年に活動を開始した。彼らは2020年秋にイギリスのレーベル、Bingo Recordsと契約し、最初のシングル「We Don’t Need Room For Lovin’」が2021年2月にリリースされ、続いてEP『Launching Moondream One』がリリースされた。それはすぐにThe Bug Clubを、前年の閉じ込められたパンデミックの退屈さに対する皮肉でライブ重視の解毒剤として確立した。BBC Radio 6のMarc Rileyは初期の擁護者だった。
『Pure Particles』が続き、そのレコード盤にはカルト的な言及が満載のボードゲームが含まれていた。彼らは従来のやり方にうんざりし、その後「Intellectuals」をリリースした。それは実際には、ストリーミングモデルを鼻であしらうテレキャスターを叩きつけるバッハへの答えのような5トラックの「ソングスイート」だった。高尚なミュージシャンは、永遠に歌詞で叩きのめされた。2枚目の単独リリース「Two Beauties」は、2022年の2枚目のリリースとなり、10月のデビューアルバム『Green Dream in F#』の登場へとつながった。翌1月、彼らは本腰を入れ、変装して、Mr Anyway’s Holey Spiritsとしてツアーで自分たちをサポートすることにした。ライブアルバムがこれを記録し、その後彼らはタイトルを抽象化し、ピクチャーディスク『Picture This!』をリリースした。2023年秋までに、47曲入りの詩に満ちた2枚組アルバム『Rare Birds: Hour of Song』の時期が来た。
アメリカへの旅行中、彼らはSub Popの目に留まり、彼らをOn the Intricate Inner Workings of the Systemで分厚いガレージパンクの塊を提供するのに間に合い、その過程で適切に強化されたアメリカのファンを獲得した。パートナーシップは実り豊かであることが証明され、Sub PopがThe Bug Clubのクラブにしっかりと参加したことで、彼らはVery Human Featuresに取り組み始めた。文学的で、自己言及的で、ユーモアのあるロックンロールの、確実で終わりのないウィットに富んだ旋風である新しいレコードは、バンドがまるでローラースケートでCaldicot Aldiの駐車場を素早く走り回っているかのように、彼らの絶えず膨れ上がる人気に乗っているのを見ている。それが長く続くことを願っている。