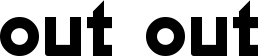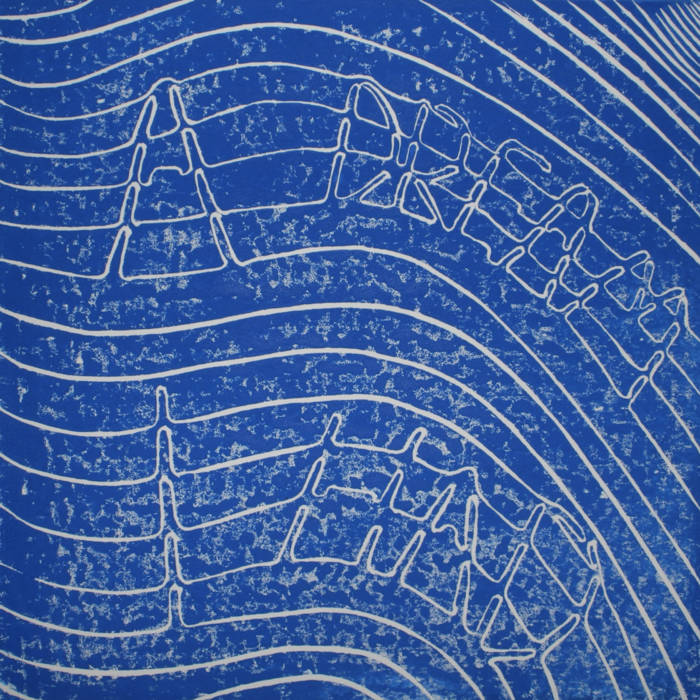ミュージシャンのDavid Fridlundは、サンタフェのWhole Foodsで6年間働いていた時の経験を語っています。彼の同僚のほとんどはメキシコとチベット出身で、彼らは「手の届かないアメリカンドリーム」を目の前にしながら、昇給もなく低賃金で懸命に働いていました。世界で最も裕福な人物がWhole Foodsを買収したにもかかわらず、彼らの労働によって富裕層はさらに豊かになる一方で、労働者は給料をやり繰りするのに苦労しました。さらに、彼らが働いていたコーヒーバーでは、会社側が「非課税の金銭」としてチップの壺(tip jar)を撤去しました。
サンタフェの街は美しく、夕日は圧倒的だったものの、Davidの私生活は「大きな悲しいスープ」のようなものでした。彼にとって、仕事に行くことがしばしば最大の安らぎの瞬間でした。彼は自分自身を外側から見ているような感覚の中で生きており、本来の自分であった時代へ戻ることを切望し、鏡に映る自分の姿に見知らぬ人の視線を感じていました。彼は「後ろの橋はすべて燃え、前進する道はまっすぐ地獄へと続いていた」と、その当時の絶望的な状況を表現しています。