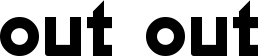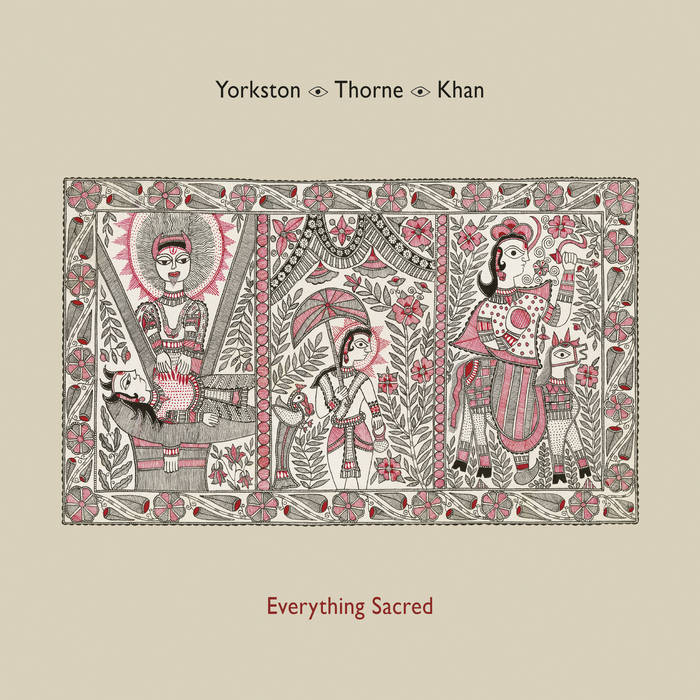ARTIST : Joan Shelley
TITLE : Real Warmth
LABEL : No Quarter
RELEASE : 9/19/2025
GENRE : folk, indiefolk, ssw
LOCATION : Louisville, Kentucky
TRACKLISTING :
1. Here in the High and Low
2. On the Silver and Gold
3. Field Guide to Wild Life
4. Wooden Boat
5. For When You Can’t Sleep
6. Everybody
7. New Anthem
8. Heaven Knows
9. Ever Entwine
10. Give It Up, It’s Too Much
11. The Orchard
12. Who Do You Want Checking in on You
13. The Hum
「私は、私の中の意地の悪さを消し去ってくれるようなサウンドを待っていた…」
Joanが、彼女の新しいフル・アルバム『Real Warmth』について、何か文章を書いてくれないかと私に尋ねたとき、私は誇らしげな意欲と、沈み込むような不安の両方で胸がいっぱいになった(計算上ではフィラデルフィアの老舗レーベルNo Quarterからの6作目だが、絶え間なくリリースされるEPやサイド・リリースがその計算をめちゃくちゃにする)。もちろん、現代のソングライティングの巨匠を世間に紹介するという名誉ある誘いに、私は喜んで応じたが…私に何がわかるというのだろう?いや、本当に、これは修辞的な問いかけではない。私に一体何がわかるというのだ?すべてについて、だ。調子の良い日なら、Misfitsが77年から83年の間に経験したメンバーの変遷を説明したり、Toy Machineの1996年製VHS『Welcome To Hell』で誰がどの曲に合わせてスケートしたかを暗唱したりできるかもしれない。しかし、Sandy Denny?June Tabor?ヒルビリー・ミュージック、ゲール民謡、アパラチアの鉱山歌、ダブル・ドロップDチューニング、あるいは個人的なことだが、子育ての初期や、このアルバムのリリース前後にJoanとその家族が着手した、比較的最近の、比較的大きな生活の変化や移転といったことについて、私が一体どうすれば明瞭に要約できるというのだろう?
ここには多くの文脈があり、Nathan Salsburgのナルゲン・ボトルの中身(またはその欠如)には、私の人生の荷物全体よりもはるかに本物のフォーク・ミュージックへの敬意が詰まっている。だが、弁護させてもらうなら、私は聞き手だ。書き手や話し手よりもずっと優秀な。このアルバムの曲に、なぜこれほど重みがあり、特別で、そして…「今」を感じさせるのか、正確に説明することはできないが、同様に、なぜ深みのあるハウスやテクノのレコードの10枚中9枚には基本的に退屈するのに、残りの1枚は(良い意味で)窓ガラスを叩き割りたくなるほどの興奮を呼び起こすのかも説明できない。私にはこれらの事を言葉にする語彙がないが、私の中の何かが深くそれらを理解している。そして理解するだけでなく、その栄養を処理し、核となる感情レベルで反応する。私は『Real Warmth』に反応する、なぜなら私は本物の温かさに反応するからだ。本物の人々に。本物の自然に。本物の化学反応に。そして、本物の錬金術にさえも。
錬金術と言えば、本題に戻ろう…Joanの曲が、それを聴く者にしばしばかける様々な魔法に、この10年間で虜になってきた私というヒキガエルは、このアルバムのオープニング曲「Here in the High and Low」の最初の1分を聴いただけで、知的に語るには全く不適格だと感じた。これは瞬時にトップ5に入るJoanieの曲だ。これは…なんてことだ。その音楽を聴くうちに、私に課せられた義務への固有の恐怖は深まるばかりだ。ソングクラフトの土壌にはある種の豊かさがあり、アルバムが進むにつれて、ほとんど超物理的な方法でこれらの曲の土壌を感じることができる。そしてアルバムは終わり、もちろん、また始まり、また始まる。3回目のリスニング、13回目、そして今や30回目…と、スピーカーから放たれる「非現実的な温かさ」に、私はますます同調し、満たされていく。
まとめようとするのは失礼を承知で、私は結局「わかった…やってみよう」と返事をした。しかし、私は『Real Warmth』のようなアルバムにふさわしい、難解で深い参照点をすべて持っているふりをするつもりはない。この作品の基盤には、もっと教養があり、より知覚の鋭い人なら、原始的から進歩的、精神的から世俗的、英国フォーク・リバイバルからアメリカの田舎のバラッドまで、そのルーツを素早くたどることができるような、広大なネットワークがある。しかし、私のような限られた理解力でも、Joanと、彼女の並外れた共感力を持つ協力者たちは、『Real Warmth』において、消えることのない集団であることは明らかだ。彼らは伝統音楽の収集家、管理者、学生、共同教育者、伝達者、目撃者、囁き手、そして人生の送り手であり、ここで彼らが確立した言語は、アレンジメントそのものがまるで会話やそよ風のようにも感じられる。
『On The Gold』のような真にクラシックに感じられる曲の後に、『Everybody』のような真にクラシックに感じられる曲が、一貫して穏やかに展開し、お互いの共有スペースに有機的に咲き誇っていく、仲間意識のような、強引さのない優しさがそこにはある。それは主観的にも客観的にも美しい。しかし、誤解しないでほしい。これは、コスプレした大衆のための「日曜日の古い町の祭り」のようなフォークの餌食ではないし、ましてや「太陽とやわらかなボール」のような時代でもない。確かに、今は夏だ(これを書いている時点では)。キッチン・テーブルに座っている私から2ヤード離れた庭で、小さな子どもが父親と犬と楽しそうに遊んでいるのが見える。しかし、彼女の世界中の政府は、地球の生物学を自己絶滅へと向かわせる政策を作り、消し去っている(これを書いている時点では)。子どもたちは爆撃で命を落としている(これを書いている時点では)。この音楽は、それについて無関係ではない…。
「だが、爆撃が速く緩く響くとき 誰が岩と農場に属するのか
あなたは足元の地面が響くのを聞く 虐げられたひび割れた大地
光景は悲しい あまりに悲しすぎて耐えられない しかし私はこの世界を歌う
幸せなメロディーは周りを回る 幻想の世界を…」
そして、最も擦り切れ、疲弊し、現実的であるときでさえ、Joanの音楽世界は最終的に、幻想ではないにしても、私たちが知っていること、私たちが何者であるか、私たちがどこから来たのかについて、甘く魅惑的なバージョンを描き出している。先ほど、これらの曲が芽生える土壌を、まるでステレオの前で床に寝転がっている私の指の間を流れる地面のように、事実上感じることができると言った。Joanがもはやケンタッキーに住んでいないことも知っているし、このアルバムがケンタッキーで録音されたわけではないことも知っているし、参加者のほとんどがケンタッキー出身どころか、アメリカ人ですらないことも知っている。それでも、私はそこに投影してしまう。すべての音符のDNAの中に、この土地の何かが深く息づいている。耳を凝らせば、湿った夏の夜空に遠くの蝉の鳴き声が聞こえるようだが、もちろん、『Real Warmth』の野原に自由に揺れている幻聴はこれだけではない。Doug Paisleyの親切で完璧に抑制されたボーカルが、レコードの中盤「New Anthem」に現れ、「Heaven Knows」でもう一曲歌ってから去っていく。まるでDougの存在が、旧友の幽霊の訪問であったかのように。カナダのパーカッショニストPhilippe Melansonのドラムは、これらのレコーディングで非常にクールで、独特の「他者」として響いているので、時々、再び耳を凝らすと、まるで微妙にミックスされた、独特のプログラミングがされたドラムマシンのように聞こえる(なぜかPapa Mの『Live from a Shark Cage』やJohn Martynの『One World』が頭に浮かぶ)。これらはより多くの幻聴だ。本物の幻聴。本物の人々。より多くの温かさ…。
聞き手(ヒキガエル)として、私は2つの状態の間を揺れ動いていることに気づく。1)バンドが、まるで魔法の絨毯のようにJoanのボーカルをしっかりと、しかし色鮮やかに支え、言葉を歌から歌へと運ぶ能力に、深く畏敬の念を感じている状態。そして2)その効果にあまりにも魅了され(そして後に罪悪感を覚え)て、もはや彼らがそこにいることに全く気づかなくなる状態。ここにあるのは安易な愛…ここにあるのはどんな安易な愛でも、言葉は想像上の静けさとともにほんの一瞬だけ上向きに漂い、その後そっと元の構成に戻っていく…しかし、アルバムを締めくくる魅惑的な「The Hum」で、バンドがほぼリアルタイムで部屋を出て行ってしまった後でさえ、彼らが藪の向こうで声をかければ届くような距離よりも遠くにいるとは感じられない。そして、この現代的な楽曲の、まったくもって光り輝くコレクションへと私たちを導いてくれた、召喚された力もまた遠くにはいないのだ。
彼らのために、彼らと共に、私たち(ヒキガエル、幻聴、友人、人間)は、皆で一丸となって意地の悪さから抜け出し、
「ハミングしよう
霊たちが私たちが来たことを聞くように
彼らがいつも私たちの近くにいるように
いつも」
― Ryan Davis、2025年7月