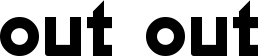ARTIST : Luka Kuplowsky
TITLE : The Grass Grows, Antonych Grows Росте Антонич, і росте трава
LABEL : Next Door Records
RELEASE : 3/20/2026
GENRE : indiepop, softpop, artpop
LOCATION : Toronto, Ontario
TRACKLISTING :
1. Ліс
2. You Are Music
3. I Am a Bug
4. The Grass Grows, Luka Grows
5. Весна
6. Plant Life
7. A Proud Plant That is Myself
8. The Home Beyond a Star
9. Spring!
10. Сурми останнього дня
11. Storm is Near
ルカ・クプロウスキー(Luka Kuplowsky)の最近の音楽的試みは、絶え間ない問いを投げかけています。「詩はいかにして旅をするのか?」という問いです。天上の響き。森の言葉。歌と朽ちゆく中へとまどろむ虫たち。無限を呟く草原の言語。塵の上に哀歌を綴る月。ウクライナのオルフェウス的詩人、Bohdan Ihor Antonych(1909-1937)の詩を歌へと適応させることは、ソングライターをある種の不確実な状態に置くことでもあります。「私は詩を媒介しているのか? ヴィジョンか? それとも感覚を超えた何らかの力なのか?」
合成音と有機的なサウンドに浸り、きらめく明るさとふくよかな温かみの中で膨らむLuka Kuplowskyの『The Grass Grows, Antonych Grows (Росте Антонич, і роステ трава)』は、目覚めながらにして見る夢を書き写す行為に似ています。強烈なイメージが現実へと溶け込んでいくのです。Bohdan Ihor Antonych自身、しばしば朝の光の切迫感の中で詩を書き、夜の夢の熱狂と旅を捉えるためにベッドから飛び起きました。田園的なユートピア主義、黙示録的なヴィジョン、そして様相を超えた共感覚の閃光を通じて、Luka Kuplowskyは、トロントの最高峰のコラボレーターたちと共に、Bohdan Ihor Antonychの詩を言語と音の予期せぬ共鳴関係へと誘う、鮮やかで輝かしい世界を描き出しています。
Luka Kuplowskyの2024年の2枚組アルバム『How Can I Possibly Sleep When There Is Music』が、禅僧で詩人のRyōkan Taiguの詩を解釈する中で生まれた詩的な繋がりの網目における「プロセス」を抱擁していたのに対し、『The Grass Grows, Antonych Grows』はその焦点を絞り、Bohdan Ihor Antonychの詩を引用しながら、レムコの異教主義、モダニズム詩、そして永遠の探求に関わる形而上学といった彼の哲学的な関心を掘り下げています。しかし、その焦点は相対的なものです。『How Can I Possibly Sleep』がRyōkan Taiguから千年の詩人たち(Du Fu、Rumi、Rainer Maria Rilke、W.W.E. Ross、Li Bai、Yosano Akikoなど)へと広がっていったとすれば、本作におけるBohdan Ihor Antonychの詩は、植物、太陽系、虫、そして宇宙まで、あらゆるものへと手を伸ばすための乗り物となっています。Bohdan Ihor Antonychは、地上的かつ霊的な超越の歌を提示します。そしてLuka Kuplowskyは、一世紀を経て、Bohdan Ihor Antonychの神話詩的な旅という循環する流れへと足を踏み入れるのです。
Bohdan Ihor Antonychは、ウクライナ詩学における際立って特異な人物です。政治的教条主義やリアリズムの外側に宇宙的な領域を提示した、アウトサイダーでありスピリチュアリストでした。当時のオーストリア=ハンガリー帝国、現在のポーランド東端に位置するレムコの村、ノヴィツァ(Novycja)に生まれた彼のウクライナ語との関係は、レムコ方言という古来の根を通じて育まれ、後にリヴィウの大学に入学してからウクライナの言語と文化に献身するようになりました。その短い生涯の中で、Bohdan Ihor Antonychは6冊の詩集(うち2冊は死後に刊行)を遺しました。それらは、のどかな田園風景という過去のイメージと、世界大戦や革命という彼の時代の混沌を橋渡しするものです。彼の詩では、植物や虫、草としての詩人という官能的なイメージが、黙示録や「火の壁」、「鐘の嵐」といったイメージと隣り合っています。彼はTaras Shevchenkoや同時代のPavlo Tychynaといったウクライナ詩の先達を継承しつつ、同時にRainer Maria Rilke、T. S. Eliot、Federico Garcia Lorca、Czeslaw Milosz、Walt Whitman、Dylan Thomasといった、現実を超越し変容させることを志した偉大なモダニズム詩人たちの列にも加わっています。ウクライナ語に外部からたどり着きながらも、西スラブ地域の土着神話に精通していたBohdan Ihor Antonychの境界的な立場は、その言語から、珍しくもありながら親しみ深くもあるニュアンスを引き出しました。それは田園的な「未来の過去」からの古の調べのようです。
Luka Kuplowskyもまた、ある種のリミナリティ(境界性)を持ってBohdan Ihor Antonychとウクライナに向き合っています。カナダでウクライナ・アイルランド系の家系に育った彼のウクライナとの関係は、言語や国家によるものではなく、文化や家族を通じたものです。彼が育つ中で参加してきた伝統的なダンス、季節の儀式、歌、そして対話を続けている詩、音楽、映画作家たちとの繋がりです。Bohdan Ihor Antonychはウクライナという国家に対して執着を持ちませんでしたが、その民衆、言語、文化の永続性を信じていました。Bohdan Ihor Antonychが国家の先にある精神性を見つめていた一方で、彼の詩に見られる黙示録的なヴィジョンは、20世紀から21世紀にかけての多大な人間的喪失に応答し、あるいは予見していたのかもしれません。アルバムの随所に、Bohdan Ihor Antonychの3つの詩の朗読がウクライナ語で挿入されています。Luka Kuplowskyの西ウクライナに住む親族が、携帯電話に向かってBohdan Ihor Antonychの一節を読み上げ、その声が農地、都市、戦場、そして海を越えて、遠く離れた場所からピンポンのように響き渡ります。
「私は虫だ」と、アルバムの3曲目でLuka Kuplowskyは唱えます。後に、彼は自分自身を一本の草の葉であると同時に、その草に向かって身をかがめる詩人でもあると想像します。超越の崇高な瞬間である「Plant Life」では、詩人の書斎での神秘的な夜が描かれ、本、植物、星が、精神的かつ肉体的な成長のオーディオ・ポエティックなモンタージュの中で合体します。Luka Kuplowskyはこのアルバムを、彼が言うところの「トランス状態」で書き上げました。Yamaha PSRを使い、Bohdan Ihor Antonychの詩を歌へと構成しながら、6日間で書き上げると同時にデモを録音しました。数ヶ月後にその曲をコラボレーターたちのもとへ持ち込んだ際、作品にはLuka Kuplowskyのデモの痕跡が残りつつも、ジャズ、ニューエイジ、コズミック・バラッドといった広い視野へと開かれていきました。ある意味で、これは非常にトロント的なアルバムです。
トロントのソングライター・エクスペリメンタリストの伝統に馴染みのない人々にとって、Luka Kuplowskyは、ジャンルを排して歌詞と音の自由な探求を行うアーティストたちのシーンから現れた存在です。アネックス地区にある「Tranzac」は、このサウンドの成長を支える中心地として機能してきました。Deep Dark United、Jennifer Castle、Sandro Perri、Eucalyptus、The Silt、Eric Chenauxといったアーティストたちが、2000年代初頭にこの独特なトロント・サウンドの形成に寄与しました。それは実験のための空間を切り開くソングライティングです。逸脱、異質なリズム、そして豊かでソウルフルなメロディに開かれたサウンド。歌と音の間の「隔たり」を掘り下げるサウンドです。これは夕食時のフォーク・ミュージックの後に深夜のフリージャズが続くような、Tranzacという空間が生んだ自然な結果です。『The Grass Grows, Antonych Grows』のプレイヤーたちはこのシーンに親和性を持っており、核となるコラボレーター(Evan Cartwright、Josh Cole、Thom Gill、Felicity Williams)は、Luka Kuplowskyと10年以上演奏してきました。これほど長い共同作業を経てもなお、本作の音のパレットは驚くほど新鮮です。Luka Kuplowskyはナイロン弦ギターを置き、Evan Cartwrightはドラム・プログラミングとジャズ特有のスプリントを調和させています。Thom Gillは主にキーボードを弾き、Luka Kuplowskyの歌声に温かなクッションを敷いています。Josh Coleはダブ的でメロディックなベースを取り入れ、Felicity Williamsは柔らかな層を成すサウンドスケープに徹しています。また、Joseph Shabason、Michael Davidson、Daniel Pencerといったトロント・シーンの重鎮たちも参加し、アルバムを美しく装飾しています。それは、Ryuichi SakamotoとDavid Sylvianのコラボレーションを彷彿とさせるとも言えますが、同時にThom GillがBerniceで見せたエンジニアリング、Evan Cartwrightのソロ作、Sandro Perriの作品でのJosh Coleの演奏、あるいはJoseph Shabason(Shabason & Krgovich、Fresh Pepper、Cici Arthurなど)の近年の活動といった、参加者それぞれの個性を認めることができるでしょう。
印象的な天上のバラッド「Home Beyond the Star」で、Luka KuplowskyはBohdan Ihor Antonychとして、天と地の結合、不可能な陶酔の追求、あらゆるものの音楽性を描写します。Walt Whitman風の再評価のように、詩人はある啓示を得ます。「私がここにいる限り/私は歌う、ゆえに私はある(I sing therefore I am)」。Bohdan Ihor Antonychの超越の歌は、Luka Kuplowskyによって引き継がれます。そして歌の中で、彼らは「ある」のです。