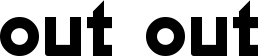ARTIST : Gregory Uhlmann
TITLE : Extra Stars
LABEL : International Anthem
RELEASE : 3/24/2026
GENRE : folk, guitar, jazz, psychedelic
LOCATION : Chicago, Illinois
TRACKLISTING :
1. Pocket Snail
2. View Above
3. Lucia (feat. Alabaster DePlume)
4. Like Tea
5. Days
6. Worms Eye
7. Burnt Toast
8. Dottie
9. Bristlecone
10. Voice Exchange
11. View Below
12. Back Scratch
13. Imprint
14. Sugar Water
『Extra Stars』は、Gregory Uhlmann の絶えず進化し続けるサウンド世界を深く美しく表現した作品であり、ロサンゼルスを拠点に作曲家、プロデューサー、ギタリスト、マルチ奏者として活動する彼の音楽の旅路において、極めて重要な局面で誕生しました。
Perfume Genius、Tasha、Hand Habits といったアーティストの長年にわたるサポート活動や、シンガーソングライターとしての側面を強調した自身の名を冠した作品群を経て、Uhlmann はここ数年、革新的なインストゥルメンタル・モダン・ミュージックのアルバムを次々と世に送り出してきました。剥き出しのメロディと静寂なアンビエントが広がる『Small Day』から、高い評価を得た Meg Duffy とのデュオ作『Doubles』、あまり知られてはいませんが同様に素晴らしい Dustin Wong とのデュオ盤『Water Map』、さらにはサックス奏者 Josh Johnson とベーシスト Sam Wilkes とのトリオによる豊かなチェンバー・ジャズ。そして、シンセを交えたトランス・ジャズ・クインテット SML の共同リーダーとしてリリースした2枚のジャンル破りなアルバム(2024年の『Small Medium Large』と2025年の『How You Been』)に至るまで、Uhlmann は現代で最も進歩的な録音物において、控えめながらも欠かせない存在としての地位を着実に確立してきました。
『Extra Stars』は、これまでの活動で学んだすべてを内包しています。輝かしい星々のセレナーデのような本作は、14曲の「極小の無限(miniature infinities)」で構成され、偶然性の高いシンセシスと計算されたメロディ豊かな楽曲が、パノラマのような音の展示場へと渦巻いています。打楽器をほとんど使用していないにもかかわらず、その音楽は極めてリズム主導であり、同時に Uhlmann は牧歌的な美しさの広がりにも深く傾倒しています。「雰囲気だけ」のアンビエント・ミュージックには欠けがちな和声的な深みに特別な注意が払われており、電子音やプロセッシングを多用した「静かなサウンド」に対する、喜びにあふれた新鮮なアプローチとなっています。
ここでの作曲とプロダクション技術は、熟練の演奏家であると同時に熱心なリスナーでもある Uhlmann の音楽性を完璧に反映しています。もし Cluster & Eno、Terry Riley の『Shri Camel』、そして Yo La Tengo の『There’s a Riot Going On』の中間地点があるとするならば、それはこの作品のすぐ近くに位置しているはずです。こうした高邁な比較はさておき、『Extra Stars』は参照や模倣を超えた先を見据えているようです。アルバムのタイトル自体、カリフォルニアの古代ブリストルコーン・パインの森(Ancient Bristlecone Pine Forest)への旅からインスピレーションを得たものであり、そこでは夜空に広がる星々の実在が、信じられる境界線を超えて広がっているのです。
私たちは冒頭から、水平線の先を見つめる Uhlmann の視線を感じることができます。アルバムのオープニングを飾る「Pocket Snail」は、ゆっくりと歩むようなシンセベースのラインで始まり、やがて豊かにプロセッシングされた、美しくスライドするメロディの残響の奔流へと開かれます。目を大きく見開くと、「ポケットに入ったカタツムリ」の小さな世界は、新鮮な太陽光の注入を受けて新しい色で溢れ出しますが、その音色はどこかシンプルなトーチ・ソング(切ないバラード)にも似ています。それは「巨大なもの」と「微小なもの」の強烈な衝突であり、アルバム全体を通して繰り広げられる、視点の見事な転換の舞台を整えています。
「Lucia」は、ビッグサーの断崖絶壁に佇む趣のあるロッジにちなんで名付けられ、親密でありながら開放的な視点を音楽的に描写したサウンドは、その名に完璧に合致しています。Uhlmann のギターのリピートが刻む安定した鼓動と響きは、カブリロ・ハイウェイの海岸に打ち寄せる遠くの激しい波のフィールドレコーディングの上に乗り、港の鐘のような金属的なパーカッションと、しっかりとしながらも柔らかな電気オルガンの和音、メロトロン風のリードによってさらに安定感を増しています。そこに、本作唯一のゲストであるサックス奏者 Alabaster DePlume が、彼独特の息づかいを感じさせるリード・ワークとともに登場します。DePlume のビブラートの効いたテナーサックスの彷徨は、何マイルも先まで広がるような音の風景に、友人同士の秘密のような親密さを加えています。Uhlmann が安定したパルスを先導する中、DePlume の低いハミングが重なり、シンコペーションの効いた倍音のピン音、羽ばたくようなリコーダーの装飾、そして太平洋岸の田舎の賑やかな物音が交錯します。「Lucia」の要素は一度耳に入ると離れがたく、わずか3分半足らずでそのすべてが美しくまとめ上げられています。遊び心と内省を等しく備えたこの曲は、読書への没頭や、あるいは遠くをぼんやりと見つめる際(thousand yard stare)の最高のサウンドトラックとなるでしょう。もし Jim Henson が『ゼルダの伝説 夢をみる島(Link’s Awakening)』を夢に見たら、こんな音が聞こえてくるに違いありません。
「Burnt Toast」は、ギターを使って「非ギター的」な音を作るという Uhlmann の嗜好を示す重要な例です。これは単なるエフェクト処理を指すのではありません。むしろ、楽器そのものをリアルタイムで劇的な音色変化をもたらすように演奏する、彼独特の即座にそれと分かる能力のことです。わずか1分25秒というタイトな時間の中で、対立しつつも補完し合うシンコペーションのブレンド??これもまた Uhlmann スタイルの特徴です??を軽快に駆け抜け、絶妙に配置されたシンセのグリッサンドやステレオイメージの揺らぎが彩りを添えます。しかし、これらを一つにまとめているのは、変容する狂騒が奉仕している「和声的なシンプルさ」です。結局のところ、「Burnt Toast」の基本構造は、極めて単純なコード進行に基づいているのです。
その本質的なシンプルさ、つまり静かな喜びや深い切望を音の表現として提示する姿勢こそが、Uhlmann の作品における最も重要な通奏低音かもしれません。『Extra Stars』において、それは7分を超える穏やかな楽曲「Days」で最もよく体現されています。この曲は、神経を逆撫でするような混乱の中にあった2020年に生まれました。「古いアパートで作ったのですが、同じコードを何度も何度も弾くことで自分をなだめる方法のように感じていました」と Uhlmann は語ります。その結果、残響を伴う伴奏がゆっくりと構築される中、ダイレクトさを維持したまま、自由な時間感覚の中を漂うような、儚く物憂げな進行が生まれました。Frantz Casseus の物悲しいフィンガーピッキングのエレガンスに Harold Budd が取り組んだかのような「Days」は、どこか懐かしい空気を纏ってスピーカーから流れ出します。祖母の家にあるような壁オルガンのメロディが、踊るようなピアノの音符の周りで歌い、お喋りするようなシンセシスが、Uhlmann のエレキギターのスティール弦の心地よさの中で打楽器的な役割を果たします。これは永遠に続いてほしいと思わせるような録音であり、おそらくどこか別の場所で、実際にそうなっているのでしょう。しかし本作において、この曲は精神的なセンターピースとして機能し、ゆっくりとフェードアウトしながらリスナーを再生させ、浄化し、次へと向かう準備をさせてくれます。
「Back Scratch」は、一連のピアノの即興演奏をコラージュして切り出し、SML のバンド仲間である Booker Stardrum によるピッチシフトされたパーカッションを加えて構成された楽曲です。不規則なループが偶然性のモードでシンコペーションを刻み、高音域の音の連打が Stardrum のスティックさばきと合流して、ドローンに近いほど密度の高いリズムを確立します。Laraaji の強烈なリズムによるチターのダンスを連想するかもしれませんが、それは厳密には正確ではありません。「Back Scratch」は、際立って生々しく、残響のない手法でプロデュースされています。その無骨で奇妙な感覚こそが、本作を『Day Of Radiance』のような作品から切り離し、Steve Reich の『Drumming』に対する地下室でのDIYな回答のように見せているのです。とはいえ、その簡潔さと『Extra Stars』の極めて多様なトラックリストの中での特異性は、(もしかすると)先の2つの名盤よりも聴いていて純粋に「楽しい」ものかもしれません。
『Extra Stars』におけるギターのない瞬間も、Uhlmann の主楽器に焦点を当てた瞬間と同じくらい明るく輝いていますが、そうした逸脱さえも、彼がコラボレーターを招き、ディレクションする際には独特の個性を発揮します。例えば、白衣を着た学者のようなシンセのふざけ心とバスケットボールが弾むようなパーカッションの「Dottie」は、「Worms Eye」のリズムが複雑に絡み合う蜂の巣のような構成と鋭いコントラストを成しています。両曲とも同じツールやテクニックを使用していますが、後者にはシンセ奏者の Jeremiah Chiu(もう一人の SML の仲間)が共同プロデューサーとして参加していることが影響しているのでしょう。それでも、Uhlmann の作曲であること、そして彼が舵を握っていることに疑いの余地はありません。例えば、「Voice Exchange」においても Chiu の存在感は確かに感じられますが、長年のコラボレーターである Tasha のピッチシフトされたヴォーカルに焦点を当てた風変わりなリズム・アプローチは、本作に収録された他の Chiu との共同プロデュース曲とは一線を画しています。
膨大なスタイルの変化を横断しながらも、それ自体が際立って認識可能な声を持つ才能たちを起用し、自らの声も失わない能力は、滅多に耳にできるものではありません。各コラボレーターのユニークな個性を Uhlmann が見抜いているからこそ、この作品は成立しているのです。その素晴らしい例が「Bristlecone」で、ここでは Anna Butterss のベースが持つ強力なローエンドの統率力と、Josh Johnson のプロセッシングされたアルトサックスが放つ多重音の神秘性を、彼が指揮しています。作曲と編曲は随所で SML の仲間たちによってサポートされていますが、その結果が彼自身のものとして明確に聞こえる範囲から逸脱することはありません。David Bowie や Joni Mitchell、あるいは Miles Davis のように、Uhlmann はコラボレーションを、支援であると同時に変容のための手段として利用しています。補強し、進化させるための手段として。長期にわたる広範かつ高次元な芸術的アウトプットを経て届けられた『Extra Stars』というこの有望なインストゥルメンタル・コンセプトの集大成。その進化をリアルタイムで体験し続けられることは、間違いなく大きな喜びとなるでしょう。