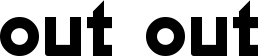ARTIST : Anteloper
TITLE : Pink Dolphins
LABEL : International Anthem
RELEASE : 6/17/2022
GENRE : jazz, modern, soul, experimental
LOCATION : Chicago, Illinois
TRACKLISTING :
1.Inia
2.Delfin Rosado
3.Earthlings
4.Baby Bota Halloceanation
5.One Living Genus
「アコースティック・ミュージシャンは電磁気によって太陽のような輝きを放ち、あらゆるものに流れ込む。これこそ、私たちが大きなシステムで演奏したいものです。雑食性、エネルギー空間、モッシュピット・ダンスミュージック。サブウーファーで鳴らせば、その衝撃を感じることができる。音楽は体から始めなければならないのだから!」 – ジェイミー・ブランチ
jaimie branch(ジェイミー・ブランチ)とJason Nazary(ジェイソン・ナザリー)がAnteloperです。自分たちの名前について尋ねられると、ブランチは韻を踏んで答える。「アンテローパーは、アンテロープのことで、邪魔者よ」さらに、「アンテロープは、パーティにやってくるけど、みんなに嫌われてるのよ」と、陽気に付け加えた。バンドが結成される前から彼女はその名前を持っていたことが判明し、デュオがリハーサルを始めると、これこそがAnteloperのサウンドであることが明らかになったのです。
デュオの新しいアルバムのタイトルには、別の生き物が登場します。ブランチは、この名前は彼女の母親から受け継いだコロンビアの伝統にちなんだものだと説明しています。「アマゾンに生息するピンクのカワイルカは、海水でも淡水でも泳ぐことができるし、汽水域の混ざった水域でも揺らぐことができるんだ。海水でも泳げるし、淡水でも冷やせる。水棲生物でありながら、絶滅の危機に瀕しているのです」。ブランチとナザリーは、様々な地形に適応し、音を通して様々な方向に動く、多くの点でそのようなイルカに似ている。
‘Pink Dolphins’ のアルバムアートワークは、主にインクとガッシュをベースにしたアーティストであるブランチによるもので、自分の絵に大量のデジタル処理を施したのはこれが初めてだという。ブランチは、FLY or DIEの最初の2作品のアルバム・ジャケットで一緒に仕事をし、彼女のためにいくつかのタトゥーも施したJohn Herndon(Tortoiseで有名)と再びコラボレートしています。Tortoiseとのつながりはこれだけではありません。’Pink Dolphins’ は、2019年に彼らがプロデューサーとして採用した Jeff Parker(ジェフ・パーカー)が関わっていることもあり、デュオにとって新たな指標となる作品となっている。パーカーはこう記している。「私はすぐに興奮しました…。Anteloperは非常にユニークなサウンドとケミストリーを持ち、彼らがやっていることすべての背後にある精神が好きなんだ」 と。
しかし、ニュー・アルバムの全貌に触れる前に、簡単におさらいしておこう。ナザリーとブランチは、10代後半にボストンで初めて音楽的に出会った。彼らの前2作、2018年の ‘Kudu’(2022年1月に初めてヴァイナルで再発)と2020年の進行中のレポート ‘Tour Beats Vol.1’ は、いずれも「コンセプトの証明」の実験として、シンセ、生の実験的デスクトップ電子機器、ガジェット、エフェクトを、パンクのエネルギーと姿勢、拡張した宇宙ジャムへの飽くなき渇きと融合させています。 ブランチは自身のバンドFly or Dieと活動し、Exploding Star OrchestraやTV On The Radio、Matana Roberts, William Parkerらと共演している。ナザリーは昨年、ヘルシンキのWe jazz Recordsからソロアルバム ‘Spring Collection’ をリリースし、Helado Negro、Bear In Heaven、Little Women、Desertion Trioなどとも共演したことがある。
Anteloperの現在の作品には、紛れもなく今と新しい何かがある。コスミッシェ・ムジーク/ポスト・パンク・サウンドのオープニング “Inia” から、スペクトルを飽和させるような激震のアルバム・クローズ “One Living Genus” まで、幅広い表現がなされている。Anteloperは、エレクトロニクスとジャズが交配された荒野で、めったに踏み入れない道を切り開いている。ジャズとエレクトロニクスは最近よくあるジャンルの相互作用だと思われるかもしれませんが、Anteloperの実験は辞書の間の未踏の空間を深く掘り下げるものです。
また、Anteloperにはパンクの側面もあり、「私たち二人ともパンクから来たのよ!」と言っています。そして、彼らのDIY、do or dieのアプローチには、そのエネルギーが感じられる。さらに、2人のミュージシャンにとってベンチマークとなるアルバム ‘Live Evil’ では、パンク以前の、マイルス・デイヴィスのような逆張りイノベーションのエネルギーを少し取り入れている。マイルスといえば、「Green Dolphin Street」(またイルカだ!)での彼のトランペットソロは、ブランチが初めて書き起こしたソロであり、ナザリーは、彼らが一緒に演奏し始めたとき、(少なくともエアトの演奏のせいもあって)『Live Evil』の「Little Church」をカバーしたいと言った。 また、パーカーが自分のお気に入りの1つとして『Live Evil』を挙げていることも、ブランチは指摘している。実際、パーカーは ‘Pink Dolphins’ でAnteloperのためにTeo Maceroのような役割を担っていました。パーカーはこう説明する。「最初に送られてきた音源は、何時間もかけて即興で作られたもので、その中から選別する必要があったんだ。圧倒されましたよ。そこで結局、Anteloperがラボに戻って、音源をより小さな塊に編集し、そこから進めていきました。グルーヴを見つけるのに時間がかかりました…何カ月もかけて、さまざまなテクニックやアイデアを試しました。私がトラックを送ると、彼らはそれに手を加えて送り返してきました。レコードを作るには、確かにチャレンジングな方法だった。たくさんのことを学びました。その価値はあったよ」
ナザリーは、デュオとしての彼らの成長は、エレクトロニクスとの関係をより洗練されたものにすることでもたらされたと述べています。「僕らにとってのもう一つのステップは、どうやってインターフェイスするか、つまり僕がドラムを使ってエレクトロニクスをコントロールするかということなんだ。私はいつも違う方法を探しているのです」 ブランチは初期に影響を受けたSun Ra、Mouse on Mars、J Dilla、そして後に影響を受けたMoor Mother、Harriet Tubman、Sam Newsomeに言及します。また、サウンドとテクニックの両面において、エレクトロニクスが自分にとって探索的な楽器であることを重要視しています。ナザリーは、彼のドラムとエレクトロニクスの機材は「本当にサイボーグのようなセットアップで、マシンは私が彼らに影響を与えるのと同じくらい私に影響を与える」と述べています。そして、意外にも彼は重要なインスピレーション源としてあるビッグ・エレクトロニック・バンドを選んでいる。「Autechreが大好きなんだ! ConfieldとDraft 7.30というレコードがそうなんだけど、あれが僕のドラムの音なんだ!」
違う方法といえば、アルバムのちょうど真ん中にある “Earthlings” は、ブランチをボーカルに起用したSFスローブルースの頭打ち曲だ(Anteloperの文脈では、彼女にとって初めてのことだ)。この曲がどのようにして生まれたかについては、パーカーとブランチがそれぞれ別の側面から語っている。パーカーが始める。「彼らのインプロヴァイズから4小節のループを作ったら、すごく良かったんだ。彼はそれをブランチに送り、ブランチはこう回想している。「LSDで軽くトリップしながらジェフのループをチェックしていたら、メロディが浮かんだんだ」。歌詞は、ブランチが “誰かとの時間を知っていて、それを無理に理解しようとするが、必ずしも理解できるものではないことを知っている”と探求したように、あるフォールアウト(’Make you/Make sense/It Makes Sense’)に対する反応として生まれた部分もあった。パーカーによると、彼女が歌詞を送り返したとき、彼はすでに彼らの即興演奏の中からループを取り出し、「その上で少しケニー・バレル風のギターを弾いたんだ。その2つを組み合わせて、完成させたんだ。ジョージ・フロイドの直後で、みんながストリートにいて、コビドなどが盛り上がっているときにやったんだ。ジェイミーの歌詞には、微妙なメッセージが込められていると思う」 また、”Earthlings” は、ブラジルのサンバの女王、故エルザ・ソアレスの後期の作品、つまり彼女がこの世にいる間に作った最後のアルバム『A Muher do Fim do Mundo (The Woman At The End of The World)』から、生のポストトロピカルの重みを感じさせるものでもある。ブランチはこのアルバムから直接インスピレーションを受けたわけではないとしながらも、2021年のRewire Festivalでソアレスとワイルドで光り輝く実験的なミーティングを行ったことを考えれば、このサウンドとスピリチュアルなつながりは驚くにはあたらないだろう。
意図的であろうとなかろうと、トロピカリアの亡霊は ‘Pink Dolphins’ のアルバム・クローズである “One Living Genus” にも呼び起こされている。この曲は、ラウドでダイレクト、せっかちで不作法、進歩を求める未来派サイケデリアの広大なムーブメント(約15分!)で、1960年代後半のブラジルから発せられたカラフルで妥協のない創造的かつ革命的な精神を思い起こさせるが、バンドが故郷とするニューヨークのモダンな文化伝播のように振動している。ドラムが深い低音を響かせ、ジェイミーのシンセがその周りを泳いでいるような、水中の洞窟のようなサウンドを完全に表現している」とナザリーは感じている。ジェフのプロダクションは、進化し続けながらも常に属人的である、我々のサウンドの静と動の両方を見事に捉えている。
このアルバムが特別なのは、このデュオが勇敢にも既知のものを捨て、あまり踏み込まれていない道へと跳躍している点だ。ここには既成のテンプレートはなく、音だけがある。出発点、その破壊、そしてテレパシーによる新しい出口の創造だけである。両者によって組み込まれたエレクトロニクスは、航行装置であり、輸送用音響船である。その結果、自由奔放で別世界の即興音楽が生まれ、未知の世界に触発され、宇宙の世界でくつろぐことができる。しかし、アンテロープのサイケデリックな宇宙音楽の原動力は、逃避ではなく、むしろ現在の超現実への完全な没入なのだ。彼らの音楽は、過去や未来の概念を破壊し、今ここにある瞬間に立ち向かい、それを受け入れるために作られている。それは、アマゾン川をサーフィンする水色をしたピンクのイルカのように、稀有で戸惑うほど美しい音楽なのだ。