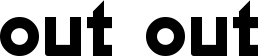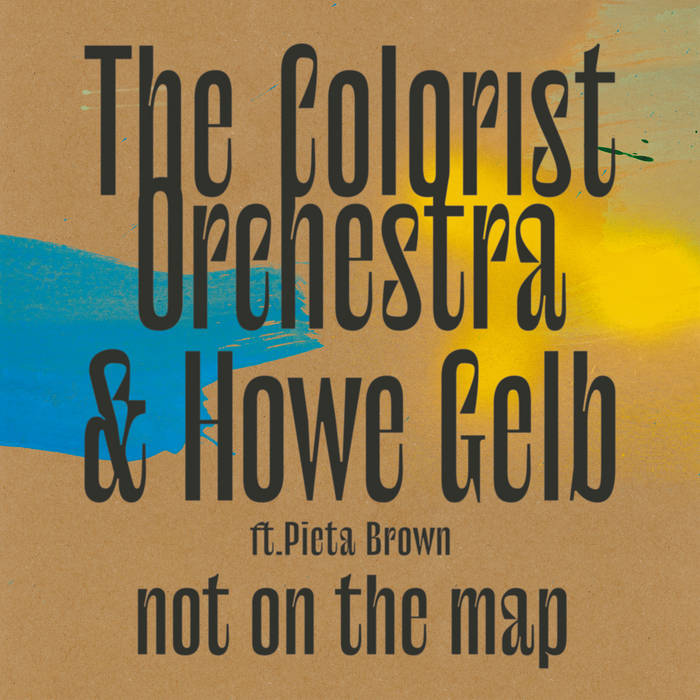ARTIST : tilt
TITLE : something we once knew
LABEL : Dear Life Records
RELEASE : 5/3/2024
GENRE : chamber, jazz
LOCATION : Brooklyn, New York
TRACKLISTING :
1.grounding i could
2.all and nothing
3.tilted
4.i try
5.a long view
6.an opening
7.mirror
8.fall again
小さな部屋の中で、tiltのサウンドがひとつの大きな声のように響き渡る。ヴォーカルのIsabel Crespo Paldoとヴォーカル/ベースのCarmen Quill、そしてトロンボーン奏者/ヴォーカルのKalia Vandeverで構成されるブルックリンを拠点とするこのグループは、緻密に織り込まれたモチーフと即興演奏が融合した、直感的な影響を与えるアート・ポップを作曲している。彼らのメロディーは両極端に刻まれ、角ばったものと痛烈に叙情的なものの間で揺れ動く。メンバー3人とも、ジャズ界で確固たる地位を築いてきた熟練のアーティストであり、作曲家でもある。彼らの見事なデビューLP『something we once knew』(2024年5月3日、Dear Life Recordsより発売)は、各プレイヤーのソロ作品とはスタイルが異なり、独自のクラスである。オーバーダビングなしでスタジオ・ライヴ録音されたこのアルバムの曲は、メンバーの特異な音楽的ボキャブラリーの神秘的な一角を通り抜けながら、理解や受容に向かう、悩み多き超現実的な旅を描いている。
tiltの作曲では、グループの楽器とヴォーカルのラインが溶け合い、呼吸を合わせる。クイルとヴァンデヴァーは、彼らの声や楽器のメロディーを歌ったり演奏したりと、流動的に行き来し、クレスポの楕円形のメリスマティックなラインと緊密に調和している。クイルが作詞作曲した「grounding, i could」の前半は、マイクチェックやチューンナップのように始まり、各メンバーが同じ音程を試し、ゆっくりとイントネーションを曲げ、予期せぬ音程をどんどん伸ばしていく。シンガーたちは、時にシンセサイザーのパッチから生み出されるような、まっすぐな鐘のような音色を奏でる。この序曲は、限られたパレットでもチルトがアクセスできる音色と表現の幅を手短に紹介してくれる。
私たちがかつて知っていた音楽は、ジャズや “ニューミュージック “に分類されるかもしれない。例えば「all and nothing」では、バロック音楽を思わせるヴォーカルのデュエットと、別室から流れ込んでくるようなメランコリックでソウルフルなトロンボーンのソロが並置されている。この曲の歌詞は、グループの音楽作りへのアプローチを明確に表しているようだ。彼らは部分の総和よりも大きく感じられる作品を作ろうと努力しており、おそらく描写や解釈の域を超えた、作品のテキストの外側に潜在する意味にアクセスしている(「彼らの言葉、一種の到達点/想像を超えた空間へ/彼らの記憶、一種の呼吸/成長しては消えていく」)。
このアルバムに収録されているどの曲よりも、クイルの「a long view」は、特に、もどかしく影のある過去を処理し、教訓を見つけることをテーマにしている。この曲は、楽器と声の間を行き来する物悲しい言葉のないメロディーと、語りかけるように歌う詩(ロバート・アシュレイのオペラを思い浮かべてほしい)を組み合わせている。歌詞は、先祖と血統を探求するクイルの日記から抜粋されたもので、この曲は、人がどのようにしてそれらとの意味のある個人的なつながりを築くのかについて声に出して考えている。グループの即興演奏は、クイルが言うように、探し求めるような感覚を呼び起こし、この曲の効果にとって重要な「まだ見つかっていない」という感覚を呼び起こす。
バンドはしばしば、注意深く協調されたグループ・ジェスチャーによってこの「まだ見ぬもの」を呼び起こすが、このアルバムで最も鋭いカタルシスの瞬間のいくつかは、チルトの個々のメンバーによる見事な名人芸のようなパッセージである。「Tiltted」でのクレスポの訥々とした鋸歯状のヴォーカルは、真っ二つに割れてしまいそうな自分を想起させる。”Torn, I feel swallowed/Torn, I feel wistful/Telling who I’ll be/I tilt unhinged”。同様に、”mirror”では、彼らのヴォーカル・ラインは、語り手が自分の姿に幻惑され、絡め取られている様子を模倣している。繰り返されるフレーズは形が歪み、強調されなくなる(「かろうじて、かろうじて鏡の中の自分を認識することができる/私が言うことすべてが、鏡の中の私に反響して返ってくる」)。このアルバムを通して、各曲の中心となる歌詞やテーマは、異例のテクニックやフレージングによってより鮮明に定義されている。
しかし最終的には、かつて私たちが知っていた何かが、共同体としての理解と新たな目的の感覚とともに、最後にズームアウトする。この曲のクローズであるヴァンデヴァーの「fall again」は、賑やかな不協和音と優雅な美しさが調和したハーモニーを持つ、見事な3声のコラールが中心となっている。ヴァンデヴァーが歌詞を朗読し、クレスポが即興で彼女と呼応して言葉を並べ替え、再構成し、最終的には詩の終わりとは違う一節で終わる: “かつて私たちが知っていたもの”。クレスポにとって、このアルバムのタイトルにもなっている歌詞は、全曲に共通するスルーラインに触れている。彼らにとって、これらの曲はすべて、”私たちが探している答えは、すでに自分の中にあるのかもしれない。
クレスポの選択は、tiltがその共有された、注意深くカスタマイズされた音楽言語を使って、混乱や不和の深く内面化された原因を探る方法を体現している。このグループは、このようなものを見るためのレンズを探しているのだ。