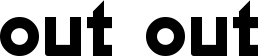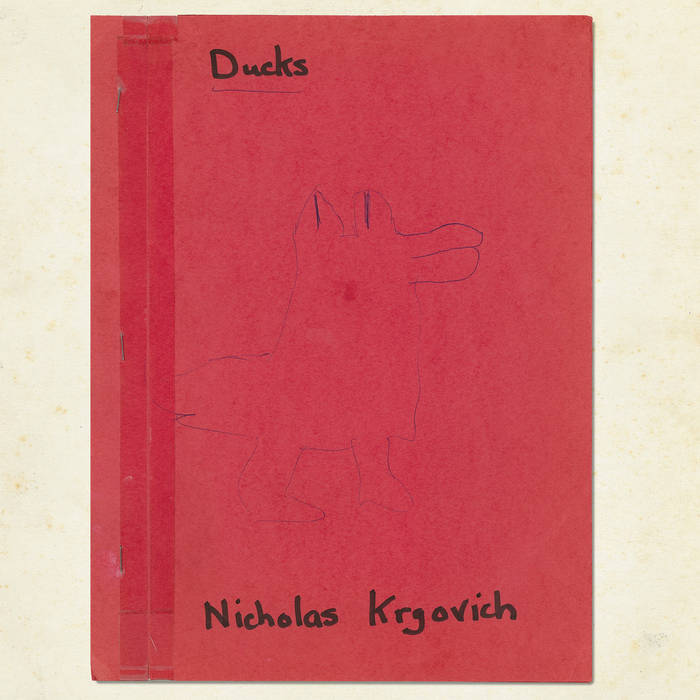ARTIST : Nicholas Krgovich
TITLE : Ducks
LABEL : Orindal Records
RELEASE : 3/10/2023
GENRE : artpop, ssw
LOCATION : Vancouver, British Columbia
TRACKLISTING :
1.Front Stoop #2
2.Coyote
3.Spring Rain
4.Ducks
5.Cup Full
6.Return
7.Rest
8.Who
9.How
10.Scorpio Rising (Grace Chen)
11.Eating Last Year’s Apples in July
アーシュラ・ル・グィンの短編小説『孤独』は、個人の絶対的な自律性に根ざした社会を描いている。この世界では、人々はほとんどすべてのことを一人で行い、森や土や空など、自分を取り巻くあらゆる些細なことを注意深く観察することで、この状態を味わうことを学ぶのです。丘の上で一夜を過ごし、頭上を旋回する星のパターンを注意散漫になることなく観察することが好まれている。また、新しい風景に一人で長い旅をすることで、見知らぬ土地で孤独な思索の喜びが強まることもある。
Nicholas Krgovichの新しいアルバム ‘Ducks’ は、同様に孤独の豊かな経験、そして最もありふれた瞬間にさえ得られる多くの静かな啓示を探求しています。このアルバムの11曲はそれぞれ、そのような瞬間にただ生きていること、感覚的であることを注意深く観察したヴィネットを提示しています。Krgovichは、手紙を送ること、暑い日に目覚めること、海岸で貝殻を探すこと、芝生を刈ること、そしてこれらの活動に対する彼自身の考えや感情に気付くことを描写しています。このアルバムの過激な存在感は、歌詞とプロダクションの両面で強調されている。どの曲も瞑想的で、耳をまっすぐな道へと導き、動きながらもどこかその場に根を下ろしているような鼓動がある。シンプルなパーカッションの上を、エアリーなギターが漂い、2、3個の音で構成されていることが多い。エッグシェイカーは正確に出たり入ったりする。Krgovichのこれまでの作品の特徴であった意外性のあるコード進行はこの作品にもあり、他の要素の規則性に加え、意外性のあるハーモニーの変化というこの組み合わせは、歌詞のテーマである「規則正しい日常の中にも発見がある」を言葉なく呼び起こすように感じられる。私たちは常に自分自身と世界に驚くことができるのです。
私は、この ‘Ducks’ を極めて中年のアルバムとして聴いているが、これは褒め言葉である。トラック1の “Front Stoop 2” は、「何年も何年も、僕は孤独だったと思うけど、そう呼ぶことを拒んでいた」という孤独の宣言で始まり、その事実を認めることが成熟の証なのかもしれないという嬉しい実感がある。「他のことはいくらでも言えるのに、どうして/素朴な質問に素朴な答えで答えるのか/私には新鮮でいい感じだ」。若者の疲弊したメロドラマはもうない。若い人の、時に魅力的で、時に不愉快なほど無自覚なところも。クルゴヴィッチはある年齢に達し、自分自身と、自分が知っていること、感じていることに心地よさを感じるようになった。最後の曲 “Eating Last Year’s Apples in July” では、「There was love in this house for a time/you brought it in」と繰り返し歌い、不快感さえも心地よく感じているのである。このように、避けられない時間の経過と、それがもたらす損失をシンプルに認識することは、確かにメランコリックだが、以前のような怒りに満ちた時代には、それが彼を押し殺してしまうことはなかったのだ。アルバムを通してのKrgovichのヴォーカルは、この中年らしさを強調している。彼の無表情な声は、決して怒ったり泣いたりせず、大きくもならず、柔らかくもならず、ただ、彼の声域が深すぎてついていけなくなり、荒々しいささやき声で、たいしたことがないように消えていくだけだ。
この曲の最初と最後の曲で示唆される孤独という枠を通してDucksを聴かないのは難しいが、他の場所では、語り手は社会性の脈打つ網に取り込まれ、その中で満足しているようだ。これもまた、中年の知恵の現われといえるだろう。思慮深い人生には、孤独についての静かな考察が必要なときもあれば、一体感の快楽を認識することが必要なときもある。この後者は、タイトル曲の ‘Ducks’ に顕著に表れている。オールドスクールなカシオの静かなビートで始まり、太いストリングスのアコースティックギターとシンセの持続音が空間を埋め尽くし、やがて曲は開花していく。ここでは、犬が遊び、アヒルが泳ぐ “A fine day in the sun/for everyone” を垣間見ることができる。そのアヒルについて、彼は “What they know seems real “と歌っている。このように、あらゆるものが「本物」であるということを喚起し、「みんな」という言葉の中にアヒルや犬が含まれていることに、健全さと過激さを感じるのである。
このような人間以外の動物が、多くの曲の中を走り回り、遊んでいる様子も、’Ducks’ に季節感や土の香りを強く与えている一因だろう。春の雨」の冷たい清々しさから、 ‘Ducks’ の晴れた夏の日、”Return” の熱い太陽と汗に変わる。数曲後にはハロウィーンになり、家の中は “カボチャのように照らされている”。一方、”Scorpio Rising” では、語り手の誕生日で、彼は「最後の甘い夏のプラム」を食べ、キーボードの単音が秋の初雪のように彼の声をソフトに響かせる。ル・グィンの短編小説と同様、’Ducks’ からは、季節、味覚、草の葉といった地上の生活の最も単純な側面でさえも、その深さと美しさを強く印象づけられる。また、注意深く観察された孤独の快楽と、その孤独にしばしばつきものの、宇宙的孤独の快楽も。