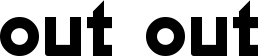ARTIST : Warmer Milks
TITLE : Soft Walks
LABEL : Sophomore Lounge
RELEASE : 8/27/2021
GENRE : noise, avant, psychedelic
LOCATION :
TRACKLISTING :
1.I See The World Tonight
2.Wild Spring
3.The Friends
4.A Bulb In The Dark
5.Patio’s Blues
6.A Strange Mirror
7.Walks
8.Steady Sheets
9.The Turth
10.Miracles
「ケンタッキー州郊外の寝室でギターを弾きながら(CDRを焼きながら)ポスト・ポスト・パンクを志す若いミュージシャンだ。Michael Andrew Turner(マイケル・アンドリュー・ターナー)として生まれた彼は、非公式なもの(Mikey Turner)、文学的なもの(M.A. Turner)、アンドロイド的なもの(Ma Turner)、神秘的なもの(Mazozma)など、一連のパンク的な名前(すべてのゲートは開いている)を巡っていく。インターネットのおかげで、彼の音楽活動は、例えば、1950年代のアメリカやヨーロッパの前衛演劇、1960年代後半の世界的な前衛サイケデリック・ロック・アンダーグラウンド、1970年代のシンガーソングライターのアウトロー・カントリー、1980年代のハードコア・パンクなどから簡単に影響を受けることができます。1980年代のハードコア・パンク、そして1990年代には、ロラパルーゾイドのMTVグランジの氷山の一角(水面下には巨大なパンク/インディー・アンダーグラウンドがある)と、サンフランシスコや日本、ヨーロッパなどあらゆる場所からの奇妙なバナナフィッシュ・ノイズの両方が登場します。それだけではなく、彼はそれらすべてに影響を受けた音楽を演奏する自分のバンドを一度に始め、その音楽を大量に録音し、それをすべてインターネット上に(CDRやカセット、時にはレコードやCDで)送り返し、生きたサブカルチャーのフィードバックループを作ることができる。
2003年にケンタッキー州のレキシントンという大学都市で結成された Warmer Milksという奇妙でパワフルな小さなコンボ・バンドで、彼は最初にそれをやってのけました。Warmer Milksのようなバンドは、2000年代に入ってから、しかもレキシントンのような場所でしかできなかったと思います。海岸沿いのメディアセンターの経済的プレッシャーやシーンターの適合性から離れていて、なおかつインターネットの全世界へのアクセスが可能なこのような場所の人々は、後期資本主義の下で得られるような芸術的に自由な可能性を持っているのです。Hair Police、Eyes and Arms of Smoke、Cadaver in Drag、Ara、Jovontaes、Jeanne Vomit-Terrorなど、この時期のレキシントンのバンドをチェックしてみてください。どれもかなり奇妙でクリエイティブなバンドですが(そして、少なくとも3つのバンドにはTrevor Tremaineが参加しています)、その中でも最も奇妙で、最も多様で魅力的な方法であると思うのは、やはり Warmer Milksです。
私が初めて Milksを聴いたのは、2005年頃にBlastitudeの住所に手作りのカバーが付いたスリムなジュエルケースのCDRが届いた時でした。カバーアートには、John Olson/American Tapes風の気味の悪いアブストラクト(つまり読めない)手書きの文字があり、内カバーの(読める)タイトルは「Family Corpse of God」というかなり恐ろしいフレーズだったので、何が入っているかは大体わかっていたのだが、聴いてみると、当時の Wolf Eyes Juniorの最新バンドによる、ただの過酷なベースメント・ノイズのリリースではないことに驚いた。それどころか、ほとんどの曲に実際のギターが使われており、実際のギターコードを演奏しており、いくつかの曲には心のこもったボーカルも入っていた。この5曲のうち、少なくとも3曲は翌年に広くリリースされている。最初の2曲は “Rwanda” b/w “Walken Agoraphobic Penn” の7インチ・シングルを構成する不可解なアヴァン・フォークのミニチュアであり(今、あなたが手にしているこのスリーブをデザインしたのと同じ Robert Beattyによる美しいアートワークが施されている)、アルバムの最後を飾る30分の大曲「Penetration Initials」は、単独のシングル・トラック・アルバムとしてリリースされた(ビーティのCDRレーベルMountaainから、そう、2つのaがある)。この「Penetration Initials」を聴いたとき、私はこのバンドとバンドリーダーが特別な存在であることを確信しました。ノイズではないどころか、ノイズロックですらなかった。これはある種の不穏で高度にプログレッシブなフォーク入り(しかしフォークに限定されたものではない)の前衛的なあらゆる音楽であり、私は楽しんだがまだ理解していなかった。
正直なところ、今でも理解できていませんが、挑戦することをやめたことはありません。当時のBlastitude誌の次号(19号、2006年1月)でマイキーにインタビューしたとき、彼は Warmer Milksが缶に入れていたアルバムの話をしました。私はまだ「Penetration Initials」の心に響くフォーキーな雰囲気に魅了されていましたが、彼は私に「調子に乗らないように」と警告していました。これは「RADISH ON LIGHT」と題されたシングルLPです。 これまでの私たちが行ってきたことについての粗雑なものは、単なる出発点に過ぎません。全面的にダメージを受ける。『Radish on Light』は数ヵ月後、2000年代のノイズロックのアンビュランスチェイサーであるTroubleman Unlimitedからリリースされたが、グロくてダメージを受けたようなサウンドというのは控えめな表現だった。このレコードは、実際にはほとんど説明がつかないものでした。ストナー、ドゥームなど、いくつかの基本的な要素を挙げても完全には間違っていないが、メタルでもなければ、他の即物的なジャンルでもない。それは、穢れた感情や思考、痛みの、煮えたぎるような、沸き立つような穴だった。「Pentagram of Sores」という曲があって、その音楽はタイトル以上に怖かった…。
この時点で、次に何が来るのかわからないのは当然だが、2008年に発売された「Soft Walks」には、まだ心の準備ができていなかったように思う。Warmer Milksのリリースのたびに戸惑うのは当たり前のことでしたが、今回のリリースはいつも以上に戸惑いました。それは、より奇妙だったからではなく、より奇妙ではなかったからです。よりローファイになったのではなく、よりハイファイになったのです。当時、私はこの作品をよく聴いていたが、Blastitudeにレビューを書くことすらできなかった。『Radish on Light』を気に入り、パート2のリリースを希望していたあるアンダーグラウンド・ノイズ・ロックの著名なレコード・レーベルは、提出後すぐに「待ちきれない!」から「ハード・パス」になったと言われている。
『Soft Walks』をパスしなかったレーベルは、偉大で常に過小評価されている Animal Disguise(Mammal、Viki、Sic Alps、Hair Police、Cadaver in Drag、Charles Lareauなどの素晴らしいレコードを多数リリースしている)で、2008年にCDのみをリリースした。その13年後の2021年になっても、このアルバムをどう表現したらいいのかわからないままだが、ライナーノーツを書いている今、何かを早く見つけなければならないだろう。『Radish on Light』が Warmer Milksの『Badlands』だとしたら、『Soft Walks』は間違いなく彼らの『Days of Heaven』である、というのはどうだろう。さて、私の中のマリック・オタクが少し無理をしているのかもしれません。正直に言うと、『Radish』は『Badlands』よりも『Hellraiser』(1987年、クライヴ・バーカー監督)に似ていたが、『Soft Walks』は間違いなく『Hellbound』ではない。『Hellraiser II』(1988年、トニー・ランデル監督)ではない。Radish』の後に公開された『Soft Walks』は、長い闇夜の後のゆっくりとした日の出であり、悪夢の中の荒々しい地獄のような風景が、実はずっと黄金色に輝く小麦畑のなだらかな海であったことを明らかにする。言ってみれば、穀物の琥珀色の波だ。マイキーのカントリーロック的な動きと言ってもいいかもしれない。
確かに、一見して、あるいは『Radish』では不可能だった快適な距離を置いた視点から見ると、Soft Walksはプロが制作した準オーケストラ的なナッシュビル・スタイルのアルト・カントリー・レコードに他ならない。ギターのTravis Shelton(トラヴィス・シェルトン)とドラムの Greg Backus(グレッグ・バッカス)は、Radishのバンドから引き継ぎましたが、それ以外の2人の新しいキーパーソン、ショーン・デイヴィッド・マクミレンとポール・オルダムを加えて、状況を一変させました。マクミレンはテキサス出身のギタリストで、チャラランビデスに隣接するグループ「Ash Castles on the Ghost Coast」(1996年にWholly OtherからセルフタイトルのCDをリリースした素晴らしい作品)に参加していたが、その後の20年間は「Catfish」(2005年、Emperor Jones)、「Dead Friends」(2010年、Tompkins Square)、「On the Clock w/JJ & Mitch」(2015年、12XU)など、大胆に揚げたシンガー・ソングライターのLPを録音してきた。彼はミルクスのツアー中に出会い、ロリンズのようにセカンド/サード・ギタリストとしてバンに乗り込み、ソフト・ウォルクスのセッションを含む在任期間を過ごしました。ポール・オールダムは、ケンタッキーで活動していたバンド「Speed to Roam」や、兄のウィル・パレス・プロジェクトでサイドマンを務めていたこともあり、マイキーの目に留まっていた。ポール・オールダムは、彼自身の隠れ家的なカントリー・スタジオでセッションを主催し、レコーディングを行っただけでなく、アルバム全体を通して非常にソリッドなカントリー・ロック・ベースを演奏している。強力なルート音を奏でるベース、カントリー/ブルース/フォーク/ロックのポピュラーなフォームに精通した3人目のギタリスト、時折、繊細なピアノや他の楽器にスライドできるメンバー(「The Turth」のメロディカかな)、そして何よりも、実際にアレンジされたバッキング・ヴォーカル(Milks初の女性ヴォーカル、アンバー・キングスレーを含む)だからだ。
しかし、このプロフェッショナルで比較的調和のとれた録音サウンドがスピーカーから流れてきても、切なく、平穏で、控えめで、愛らしい短いインストゥルメンタルのオープニング・トラック「I See the World Tonight」が、2曲目のアンセムのような憧れのヴォーカル入りのトラック「Wild Spring」へとファンファーレを奏でても、事態はまだ落ち着きません。昼間だからといって、暗闇が超越されたわけではない。『Radish」が暴いた病気や神経の損傷は、琥珀色の外見のどこかに隠れていても、まだそこにある。『Radish on Light』の生々しい笑い声やうめき声のような憑依の儀式に比べれば、確かに洗練された高機能なものではあるが、それでも彼の声には何か毛むくじゃらのような、悲しげな、寂しげな、そして剥き出しのものがあり、憧れが叫び声や怒鳴り声になるかもしれないが、完全には変化しないような、強烈な感情の分岐点にぶら下がっている。
Larry “Fuzz-O” Dolman / 2021年、1月