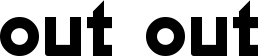ARTIST : Pedro The Lion
TITLE : Havasu
LABEL : Polyvinyl Records
RELEASE : 1/20/2022
GENRE : indierock, rock
LOCATION : Seattle, Washington
TRACKLISTING :
1.Don’t Wanna Move
2.Too Much
3.First Drum Set
4.Teenage Sequencer
5.Own Valentine
6.Making the Most of It
7.Old Wisdom
8.Stranger
9.Good Feeling
10.Lost Myself
レイクハバスは、丘陵地帯の曲がりくねった道路が続く地域で、1960年代にロンドン橋をレンガ造りに作り直したのが始まりです。Pedro The Lionの David Bazan(デヴィッド・バザン)は、中学1年生のときに1年間アリゾナの街に引っ越したことがあります。バザンは2019年の ‘Phoenix’ のために、彼の最も初期の子供時代の経験を収集した。この多作なアーティストが Pedro The Lion名義に戻ることはめでたく、彼の過去の家を記録した5枚のレコードからなる予定のシリーズの第1作目である。その続編を書くために、バザンは数年かけてハバスを4回訪れ、中学時代のキャンパスや魔法のスケートリンクなど、長い間抑えられていた感情を呼び起こす懐かしい場所を車で通り過ぎた。「30年間覚えていなかった交差点が、隠された記憶を呼び起こすのです。できるだけ、そこに浸っていたいと思っています」
ハヴァスの湖畔の複雑なループをドライブしながら、バザンはトム・ペティの伝記をオーディオブックで聞き、やがて心の中でペティの声と対話するようになった。その中で、ペティが無意識のうちに自分への優しさのために「Wildflowers」という曲を書いていたことを知り、バザンは若い自分への寛容さをもって、自分の作品に取り組むようになったのです。「あの子のそばにいたかったんだ」と彼は言います。「12歳の子どもは、まだ子育てが必要であり、処理する必要があるのです」
バザンは、自分の過去を率直に見つめ直すために、それまで必要なものとして受け入れていた有害な仕事の習慣を改めました。「それは、締め切りをなくし、心が動いたときに遊びの時間を積み重ねるということです。私はそこからゆっくりとした旅を続けているのです」と、彼は明言する。’Havasu’ になるまでの音楽制作では、柔軟性と好奇心がアレンジに反映された。バザンは、シンプルなシンセサイザーとドラムマシンのセットアップで作曲を始めた。その後、より精巧なアナログ電子機器に移行し、オリジナルの両手キーボードのアレンジを指弾きのアコースティック・ギターで木管化した。
また、ライブストリームで毎週開催されるコンサートのために楽曲を勉強し直すと同時に、ソングライティングに対する感謝の気持ちを新たにしました。「20年間、自分のケツを蹴り続けてきたことの見返りは何だったのか、考えてみたんだ。しかし、私の歌の庭は、私が築いてきたものです。エゴのテストである必要はないんだ」自分のディスコグラフィーに感謝しながらアプローチすることで、バザンが安っぽいものとして退けていた幼少期の音楽に対する認知的不協和を和解させることができた。「子供の頃、リチャード・マルクスの曲が流れると、私はうっとりしていたものです。私はずっと、そんなことはなかったことにしようと努力してきたんだ。そうすることで、自分自身を見ることができたんだ」と彼は認めています。
共同プロデューサー兼エンジニアのアンディ・D.とスタジオに入ったとき、彼はこう言いました。パーク(’Phoenix’ で同じ役割を果たした)とスタジオに入ったとき、バザンは荒涼とした、砂漠の影響を受けたレコードを作ろうと計画した。しかし、2人はすぐにペドロのクラシックなサウンドに近いロックな構成が、この風景と物語を最もよく伝えると悟った。ドラムマシンを使うつもりだったが、実験的にスクラッチドラムキットとベースを置いてみたところ、スムーズでリニアなサウンドになった。翌日聴き返してみると、このリズムセクションの最初のテイクには喜びと安らぎの感覚があり、レコードのテーマである精神的な癒しを増強していることがわかる。クラリネットからドラムに持ち替えたバザンの人生を忠実に描いた “First Drum Set” は、音楽的な自己発見の爆発的な喜びを、愛にあふれた鼓動のように、勝利のフィルに構築している。また、”Teenage Sequencer” では、心と体の断絶によるガタガタした不安を、不穏なベース、揺れ動くギタースライド、希望に満ちたタンバリンで、13歳の変わりやすい端境期にある、砕けた浮き沈みを表現しています。「自然が私をシーケンサーのように動かしている」とバザンは歌い、疑問を投げかける。「私はずっとティーンエイジャーなのだろうか?」また、”Making the Most Of It” では、ダウンテンポのアルペジオ・ギターにスタッタリング・ハイハットが添えられ、隠された感情との戦いに遊び心を加えている。とバザンは肩をすくめる。しかし、この音楽が持つ対照的な楽観性は、軽さと重さの両方の感情を伝えなければならないという要請を反映している。
ソロや Pedro The Lionの作品によく見られるように、バザンはほとんどの楽器を自分で作曲、アレンジ、演奏しているが、’Havasu’ に必要な自己受容の優しさを見つけるために、数人の重要な協力者がいた。Pedroのライブドラマーである Sean T. Laneは全ての曲に参加しているが、”the bike” と呼ばれる自作のノイズを出す楽器を演奏している。自転車のフレームに様々な金属と弦を取り付け、コンタクトマイクを装着し、ドローンを強調するペダルボードを通して演奏しています。「パーカッシブにも、アンビエントにもなる。まさに悪夢のようなマシンだ」とバザンは語り、”Own Valentine” の「切なく、メランコリックで、ギルティプレジャーなロマンス劇」的な展開と対をなす、脅威的なサウンドを強調しています。長年のコラボレーターである Andy Fittsと一緒にシンセサイザーのセットアップを探求する温かい時間が、”Too Much” の執拗なニューウェーブサウンドにつながったのです。そして、アルバムのオープニングであり、映画のようなシーンセッター “Don’t Wanna Move” では、Pedroのギタリスト Erik Waltersが最初に考案し、’Phoenix’ のクローザーで使用されたリフが登場している。「この曲でアルバムのオープニングを飾ることができ、とても嬉しかった」とバザンは言う。「レコードの間に流れを作ろうと思っているから、もし人々がそれに関わりたいと思えば、そこに何かがあるんだ」とバザンは言う。
シリーズの次の3枚のアルバムはまだ完全に書き終えていないが、バザンは現在、『Phoenix』と『Havasu』を合わせて、伝統的な3幕構成の完成された説明文として理解している。「私の家族、両親、そして私の愛する人たちが、いかにして国家主義的、権威主義的な宗教に取り込まれていったかを描きたいんだ」と彼は言い切る。「そのための種を蒔いているのであり、私自身の責任もその一部なのです。このように慎重に構成することで、後の暗い物語への道を開いているのだが、バザンはハバスに戻ることで精神的にも音楽的にも癒されることを断固として強調している。「ハバスに戻ってきたことで、私は傷つきやすい選択をすることができ、背を向けたくなかった若い自分の一部とつながることができました」と彼は言います。「私は多くの自己判断に取り組み、このレコードでは、これまでのどの曲よりも自分自身に優しくなった」 その結果、恥ずかしさと高揚感の両方を素直に認め、広々としながらも繊細にアレンジされ、その感情が育まれるに値することを肯定している–たとえ、検証を必要としていた子供がとっくに成長して離れてしまったとしても。